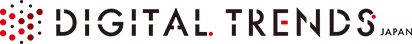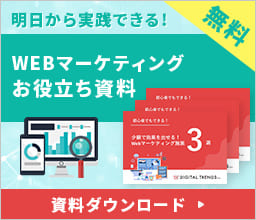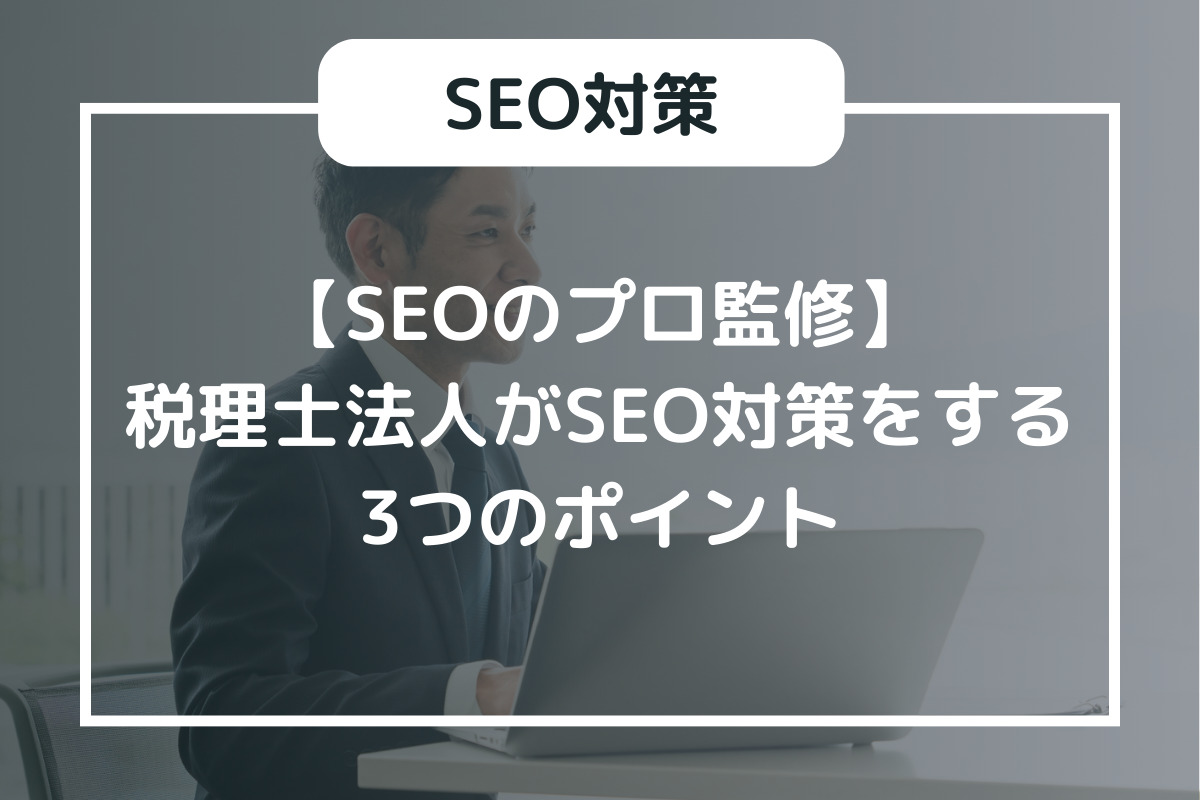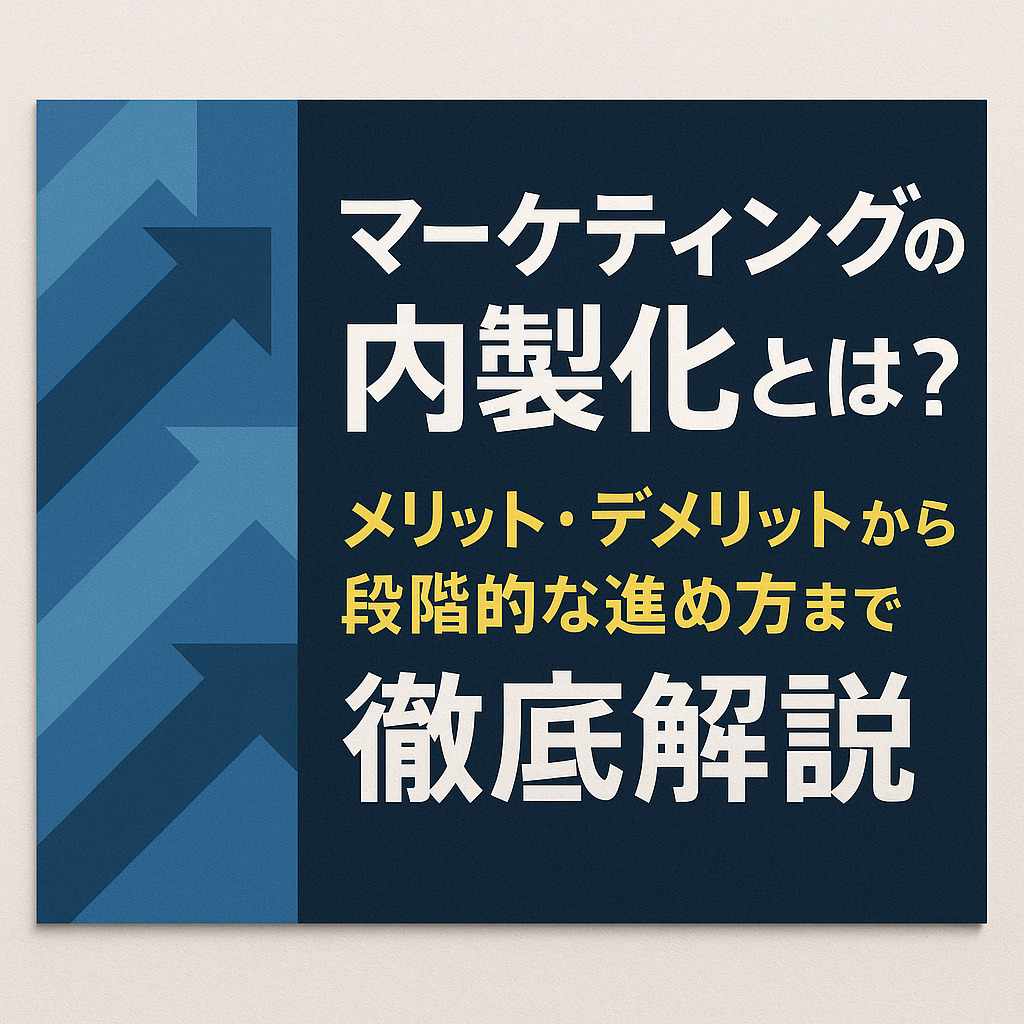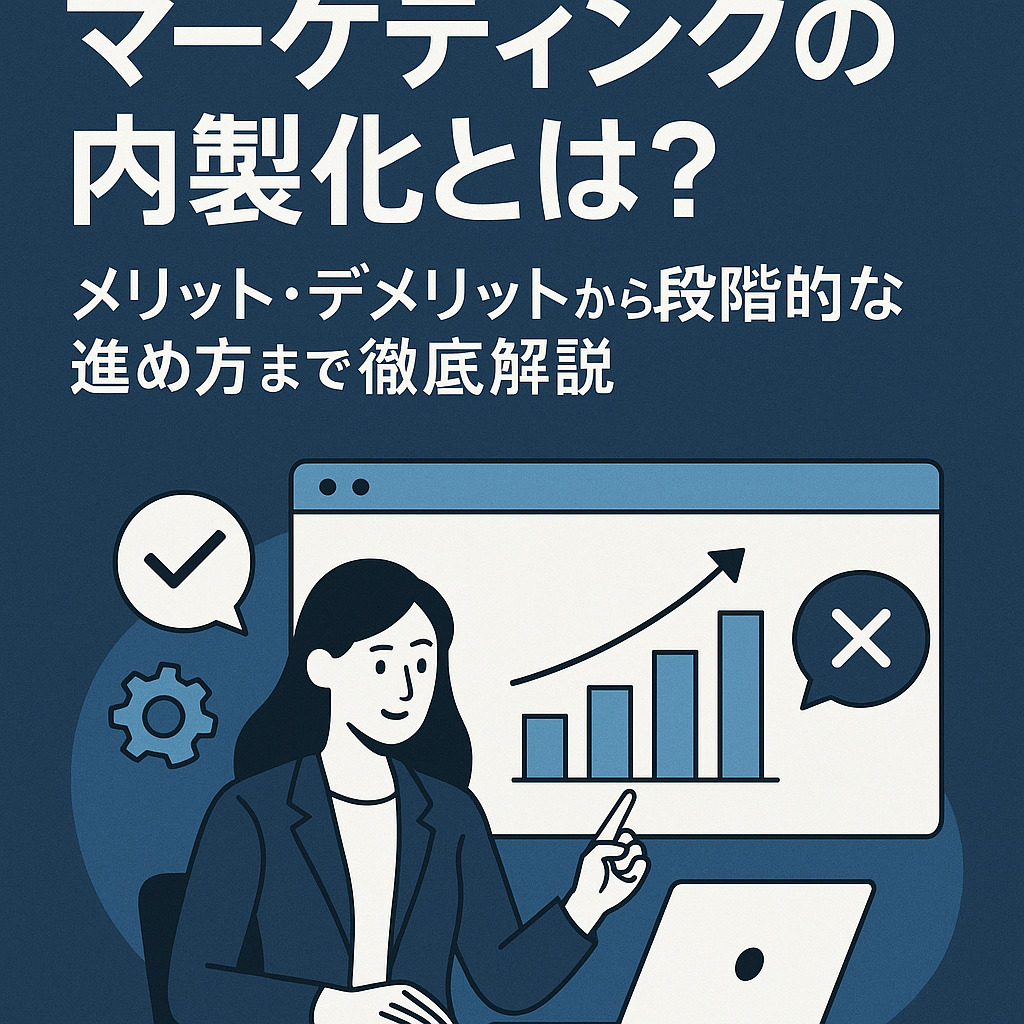オウンドメディアの立ち上げの流れ|方法・手順・ステップを解説!

オウンドメディアの設計・作り方(立ち上げ)の手順
それでは、企業がオウンドメディアで成功するためにはどうすればよいのでしょうか。
オウンドメディアの運営における成功へのプロセスを解説していきます。
1.環境設定
オウンドメディアを作るための環境設定ですが、以下の3種類があります。
- ドメイン取得
- サーバー環境を整える
- サイトデザイン、CMSの決定
ドメイン取得
ドメイン取得とは、インターネット上での住所を決めるという意味合いです。
目的地に辿り着くためには、その目的地の住所が必要になります。
その住所がドメインです。ドメイン所得サービスで会社名.comや会社名.co.jpなどのドメインを作ってください。
既にホームページを作っている会社の場合は、新規ではなくサブドメインの取得がおすすめです。
サブドメインを取得すると、Googleから既存のドメインと関連していると認知されやすいので、検索上位に上がる期間が短縮できるからです。
企業の問い合わせにつなげやすいのもメリットですね。
サーバー環境を整える
サーバー環境は、クラウド型のレンタルサーバーが人気になっています。
その理由は、オウンドメディアはアクセス数が短期間で上下しやすい特徴があるからです。
アクセス数に合わせてサーバーの容量や設定をこまめに変更できるのが、クラウド型のレンタルサーバーの特徴です。
クラウド型のサーバーを利用すれば、プレスリリースを定期的に発信する際も容量を気にする必要がありません。
サイトデザイン、CMSの決定
サイトデザインとCMSの決定では、オウンドメディアのデザイン面を決めます。
どんな文字や文章を入れるか、配置をどうするかなど、読者目線でのデザインを意識してください。
必要以上に凝りすぎてメディアの読み込みが遅くなってしまっては、離脱率が上がってしまいGoogleからの評価が下がってしまいます。
CMSは色々な種類がありますが、一番人気の「WordPress」を選んでください。
WordPressは多くの人が設定や編集に慣れているので、手順を調べたり外注化したりする際に便利だからです。
無料で好きなテーマ(デザイン)が選べるので、初心者でも見栄えの良いオウンドメディアを作れます。
2.KPIとKGIの設定
そもそも、オウンドメディアのゴールはそれぞれの企業によって異なります。
自社のマーケティング課題を認識し、それを解決するための目標を設定する必要があります。
以下は具体例ですが、目的が複数ある場合は優先順位決めることも重要です。
- 自社製品や企業の認知度向上
- 新規顧客の増加
- 既存顧客のエンゲージメントの向上
- オンラインの商品購入者の増加
- 会社のブランディング
- メールマガジンの読者の増加
- オウンドメディア自身でマネタイズ
オウンドメディアの運営など目標や成果が曖昧になりがちな分野では、KGI(Key Performance Indicator)やKPI(Key Performance Indicator)の設定が非常に重要です。
数値的に測定可能な基準を設けることで、進捗状況を客観的に判断できるようになるからです。
KGIは最終的な目標が達成されているかを計測するための指標で、その過程を計測するための中間的な指標がKPIです。
例えば、ECサイトにおけるKGIは売上高で、KPIは流入数やCVRなどになります。
3.ターゲット(ペルソナ)の選定
目標を決めたら、最終的にサービスや商品を提供するターゲットを絞ります。
ターゲットが曖昧なままだと、どのユーザーのニーズも満たせない商品になってしまい、顧客の獲得につながらない可能性があります。
また、ターゲットによって同じ内容の記事でも、書き方や順番が変わってくる可能性があるので明確に決めるようにしましょう。
良質な記事を作るためにも、誰にとって有益な記事を作るのかをはっきりさせておく必要があります。
ペルソナとはターゲットとする理想の顧客像のことです。
チームのメンバーで具体的なイメージを共有するためにも、価値観から生活スタイルまでできるだけ細かく設定する必要があります。
ペルソナに沿ってマーケティング戦略の決定がされるので、非常に重要なステップの一つです。
4.ワイヤーフレームの作成
ワイヤーフレームとは、オウンドメディアの設計図、またはレイアウトのことです。
レイアウトとは、テキスト・図・写真の配置や割付のことになります。
ワイヤーフレームを作る目的は、製作のための下書き、製作チーム内での共有、クライアントへの提案の3つです。
ワイヤーフレームを作ることで、製作関係者と内容の共有ができ、意思統一をすることができます。
おおよそ60〜70%の出来でよく、第3者が見ても意味が理解できるようにすればOKです。
できるだけ実際にオウンドメディアを作るツールで作ることをおすすめします。
5.コンテンツの構成・作成
全体の戦略策定・企画が完了したら、次に作成するコンテンツの構成づくりに移ります。
対策するキーワードや記事の目的に沿って、記事の構成案を作るようにしましょう。
ライターへの執筆外注を検討している方は、特に構成案の完成度にこだわるようにしましょう。
コンテンツの構成案が作成できたら、実際に制作、執筆に取り掛かっていきます。
ライティングの際の、SEOのテクニックはいくつかありますが、1番はとにかくユーザー目線で、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを作ることが1番重要です。
6.導線の設計
キーワードを元に記事の構成や文字数を整え、導線の設計をしていきます。
ここでも、想定読者の存在を忘れてはいけません。
常に想定読者の顔を浮かべながらコンテンツ内容の設計を行うことで、記事単位ではなくサイト全体での方向性が定まります。
キーワードや記事の構成は、あくまでも想定読者に適切に情報を届けるためのテクニックです。
それを目的と履き違えてしまう方もいますが、読者ファーストの姿勢は忘れないでください。
7.効果計測、改善の仕組みを整える
PDCAサイクルを活用する
PDCAサイクルとはPlan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のプロセスのことを指します。
例えば、「1カ月でサイトのアクセス数1万アップ」という目標を定め、それを達成するために「1日1本記事を書く」という計画を実行していきます。
時期が来て達成できなかった場合はその原因を分析します。
その結果をもとに改善策を考え、内部コンテンツの質向上や業務の改善を目指します。
データ分析ツールの活用
検索エンジンが向上したことで、コンテンツの質が非常に重要となってきました。
Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールでユーザーの特徴や滞在時間などを分析します。
サイト内のマウスの動きやクリック数、スクロール達成度などを分析するヒートマップツールなども活用して修正点を洗い出します。
その結果を元に、上位表示されていないページや滞在率の悪いページを改善していきます。
デジタルトレンズへお気軽にご相談下さい。
オウンドメディアの目的を整理
ここまでお読みいただいた方にとって、オウンドメディアの立ち上げに必要な手順やステップはご理解いただけたかと思います。
ここからは改めてオウンドメディアの目的を整理することで、制作から運用までのイメージがより一層湧いてくるのではないかと思います。
伝えたい情報を発信するため
まずはこれに尽きるでしょう。
情報の無いオウンドメディアはほぼありません。
自身の経験や好きなものをもっと多くの人に知ってもらうためにオウンドメディアを立ち上げる人が多いです。
はてなブログやGoogleが提供するblogerというサービスもありますし、サーバをレンタルすればwordpressで思い通りにサイトを立ち上げることができます。
今や、自身のサイトを持ち、情報を発信するハードルは極限に下がっていると言っても過言ではないでしょう。
広告収入でお金を稼ぐため
オウンドメディアが新しいビジネスになりました。
というのも、オウンドメディアを運営することで広告収入を得ることができるからです。
ただし広告収入を得るためには、長い年月と、ある程度のサイトへの訪問客数が必要になります。
訪問客数が多い場合は、サイトに関連する企業から「サイトに自社の広告を掲載させてくれませんか?」とオファーが来ることがあります。
そこで掲載料の交渉をすることができます。
一方で、訪問客数がまだそれほど多くない場合は「このサイトに広告を掲載しませんか?」と宣伝する必要が出てきますし、「広告を掲載してくれるサイトを募集してます」という募集を探して、広告を掲載することもできます。
訪問客数が多ければ、この広告収入が安定して入って来るようになります。
この広告収入を得るためにオウンドメディアを立ち上げ、サイトの更新に力を入れる人も少なくありません。
自社の商品やサービスを宣伝するため
企業で取り扱っている商品やサービスの購買促進のためにオウンドメディアを運営しているところがあります。
他社の商品との違いや、実際にどんなことに役立つ商品およびサービスなのかを宣伝できる場所が以前では非常に限られていました。
しかしこのオウンドメディアが普及してきたことにより、自身のサイトでそれらの紹介ができるようになりました。
サイトに訪れた人も、そのサイトが発信する情報が欲しくて、または興味があって来ているわけですから、顧客獲得を効率よく行うことができます。
会員数を増やすため
オウンドメディアは、趣味やボランティアの会員獲得および年会費を払うことでサービスを受けられる会員獲得につながります。
会員を募集する際はその会に興味を持つ人を探さなくてはいけません。
しかしオウンドメディアならば、もともとその会が発信する情報に興味を持つ人が集まってくれるわけですから、そのまま会員になってくれるよう会のメリットや、特典について宣伝することで会員数を増やすことにつながるのです。
自社の人材採用強化のため
自社のいいところ、または社員紹介などを自社が運営するオウンドメディアに掲載することで、社員の獲得を目的としている企業があります。
企業の公式サイトだけでは伝えることができない社内情報や、イベントの様子などを掲載し、企業のイメージアップを図ると同時に人材の獲得に繋げます。
実際に、入社志望の人の中には企業のオウンドメディアを見て来たという人もおり、その会社に本当に興味を持ってくれたわけですから、良い人材を獲得しやすくなるのです。
オウンドメディア運営のメリットとは?
その情報を求めている人だけが見に来てくれる
情報を発信しても、誰かに見てもらわなくてはいけません。
しかもその情報に興味を持ってくれる人に見てもらいたいはずです。
サイトに訪れる人は、気になる情報を検索してたどり着きます。
そのため、サイトが発信する情報に興味があるわけですから、見て欲しい人に情報を見てもらうことができます。
やみくもに不特定多数の人へ宣伝するよりも効率よく情報の読者を見つけることができます。
営業がいらない、広告費用が少なくて済む
商品やサービスを宣伝するために、以前はイベントに出店したりお客様先に訪問したりしていました。
しかし自社でオウンドメディアを立ち上げて、自由に宣伝することができます。
しかも宣伝費用がほぼかかりません。
(レンタルサーバ代や、プロにサイト製作を依頼する場合は製作費用がかかる)
実際に、オウンドメディアを立ち上げたことがきっかけで自社知名度が上がり利益も上がったという企業が少なくありません。
例えば、文房具メーカの株式会社コクヨは「WORKSIGHT」というオウンドメディアを持っており、自社の働き方や文房具のアイデアや商品の紹介などを通じて、利益を上げることができました。
また、無印良品が運営しているサイト「くらしの良品研究所」では、生活上のお悩み解決を商品を通じて紹介しており、紹介された商品の売上増加につながりました。
自身および自社にファンがつく
以前まで人と人は、実際に会わない限りつながることがなかなか難しかったでしょう。
しかしオウンドメディアを高頻度で更新しサイトの訪問者数を上げると、更新するたびに訪れてくれるお得意様やファンができることがあります。
そしてそのファンがサイトを宣伝してくれることで、更に多くの人に宣伝することができます。
更にそのファンは、自社の商品やサービスを購入してくれる大きな顧客になる可能性が高く、そのような上質客に巡り会える可能性が上がります。
広告収入が入る
サイトへの訪問数を増やし安定した広告収入が入ってくれば、非常に大きな利益になります。
企業から広告掲載のオファーを受け、宣伝し成功すればまた新しい企業からオファーが。
というように良い循環を作り出すことが大切です。
プロブロガーの中には月に数十万から数百万稼ぐ人もおり、これだけで生活している人もいます。
サイトを立ち上げたら、まずは訪問客数が伸びるよう試行錯誤しながら更新を続けるといいでしょう。
オウンドメディアと公式サイトの違いについて
企業が運営する公式サイトとオウンドメディアには、それぞれ異なる目的があります。
公式サイトは、企業情報の公開や自社ブランディング、求職者への採用情報の提供などを主な目的としています。
これに対して、オウンドメディアは主にマーケティングを目的として活用されることが多いです。
とくにBtoB商材の場合、公式サイトだけで直接成約につながるケースは多くありません。
そのため、オウンドメディアでは、資料請求や見積もり依頼、問い合わせなどのCTA(Call to Action)を設け、商談につなげていくことが重要になります。
企業によっては、公式サイトとオウンドメディアを分けずに、一体化して運用しているケースもあります。
BtoB領域ではこのようなスタイルが主流となっているため、以下では「公式サイトと一体化したオウンドメディア」を前提として説明を進めます。
公式サイトとオウンドメディアの主な役割
【自社公式サイト】
- 企業情報の公開
- 自社ブランディング
- 採用情報の提供(求職者向け)
【オウンドメディア】
- 自社商材の訴求
- 商談創出
- 顧客の購買プロセスに対応したコンテンツの提供
BtoBオウンドメディアに求められる役割
BtoB向けのオウンドメディアには、以下のような役割が求められます。
- 潜在顧客との初期接触の機会をつくること
- ブランドに対する理解や共感を深めてもらうこと
- 公式サイトでは伝えきれない周辺情報を補足すること
- 購買プロセスの各段階に合わせたコンテンツを提供すること
- 問い合わせや相談会申込み、見積もり依頼といった商談への導線を設けること
BtoB商材はBtoCとは異なり、購入までの検討期間が長く、関係者も複数にわたる傾向があります。
また、金額が比較的高額になることも多いため、購入の際には社内での合意形成や決裁が必要になるケースが一般的です。
そのため、「なぜこの商材を導入するのか」を社内で説明・納得してもらえる材料を提供することが大切です。
デジタルトレンズへお気軽にご相談下さい。
【SEOを始めたい方必見!】コンテンツマーケティングで効果を出す5つのポイント

コンテンツマーケティングをこれから始める企業様に向けて、コンテンツマーケティングの基本とメリット、成功させるポイントについてまとめました。
今すぐ資料を無料ダウンロード