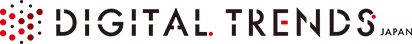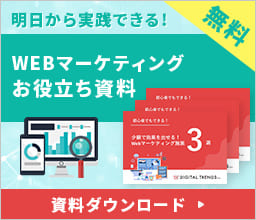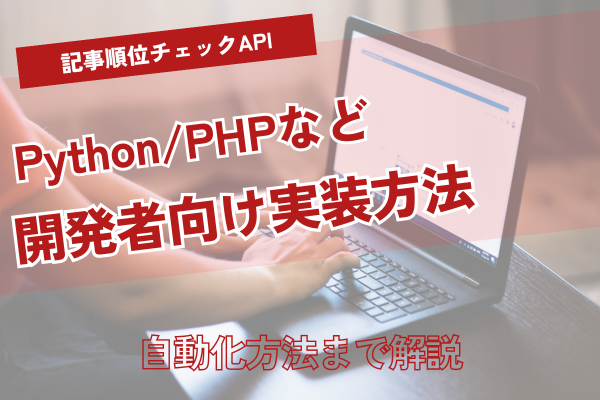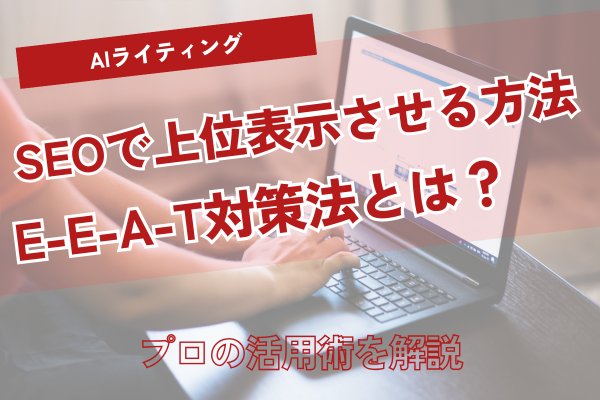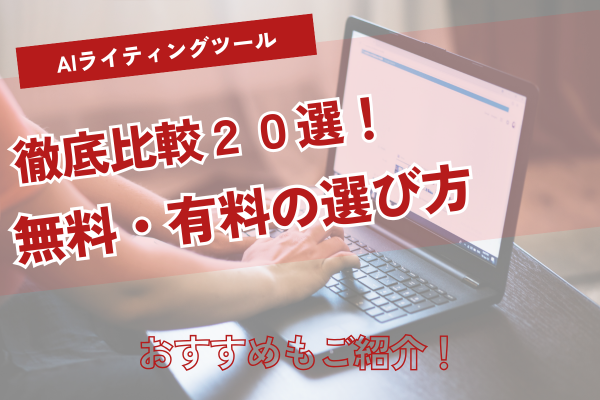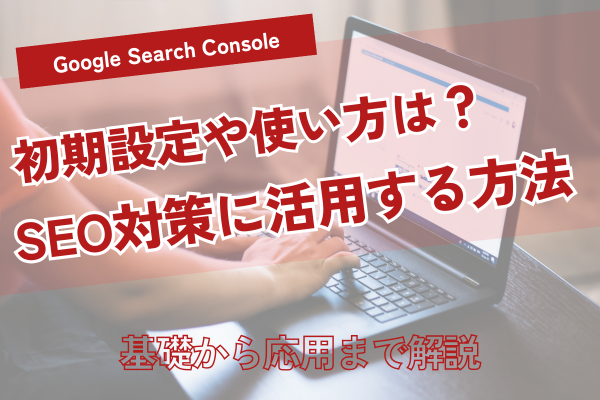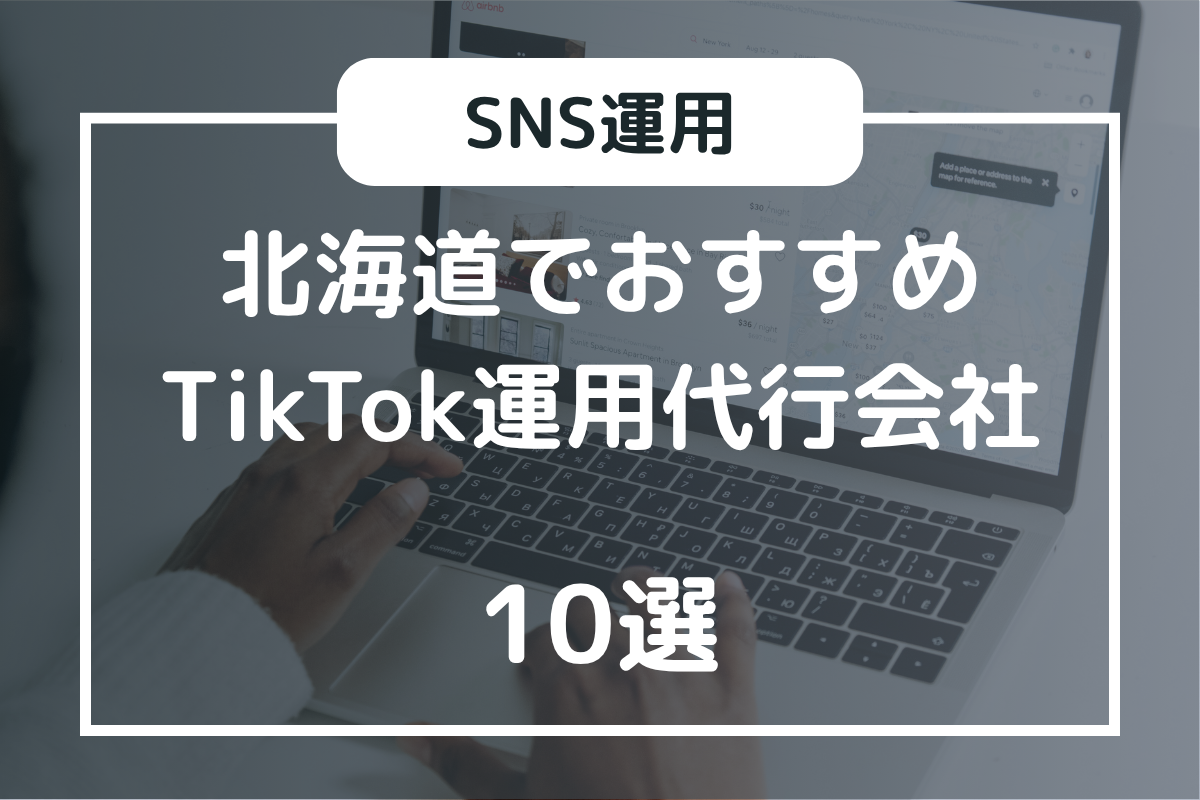TikTok運用はインハウスで強くなる!外注せず社内で運用したい企業のための内製化ガイド
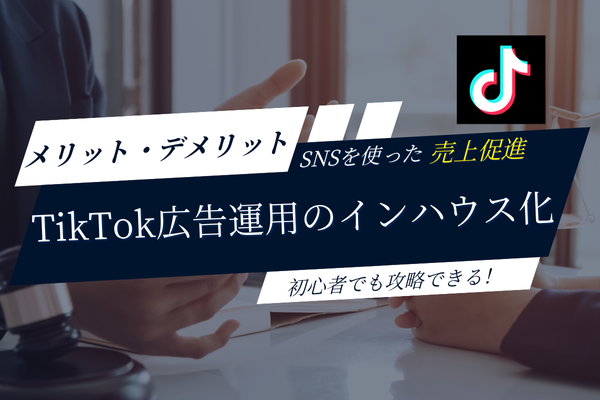
TikTokは、企業の魅力やブランドを伝える際の効果的なツールです。
適切な運用によって、企業にさまざまな利益をもたらします。
本記事では、社内発信によるリアルな情報発信の重要性や目的別にみたインハウス運用と外注の向き不向き、インハウス化のメリット・デメリット、運用体制づくりのポイントまで解説します。
TikTok運用で成果を出したい場合は、ぜひ参考にしてください。
成果を出すTikTokは、“社内発信”でこそ伸びる理由

結論として、TikTokで成果を出す企業アカウントには「社内発信」のリアルな情報が欠かせません。
今のTikTokユーザーは、作り込まれた演出よりも、発信者の本音や共感できる文脈を重視しています。
投稿の演出力よりも、発信者のリアルさ・文脈の共感が重視される
TikTokは短尺動画が主流で、視聴者は一瞬で「自分ごと」と感じるかどうかを判断します。
外部制作会社による高品質な映像は、広告色が強くなりがちで、ユーザーに距離を感じさせることがあります。
一方で、社内メンバーが現場の空気や日常を自分の言葉で発信すれば、そのリアルさや親近感がダイレクトに伝わります。
たとえば、現場社員が仕事の裏側や本音を語ることで、視聴者は「この会社で働く自分」をイメージしやすくなります。
こうした共感が、動画の拡散やファン化につながるわけです。
外注の“動画品質”より、内製の“納得感”が届く時代
従来は「動画のクオリティ=成果」と考えられがちでしたが、TikTokのアルゴリズムは「共感」や「エンゲージメント」を重視します。
そのため、内製動画は現場のリアルな声や熱量をそのまま伝えられ、視聴者に「納得感」を与えやすいのです。
外注では表現しきれない細かなニュアンスや現場ならではの空気感が、コンテンツの強みになります。
今は「本物らしさ」が評価される時代です。
企業の内側から発信することで、ブランドの信頼や共感を獲得しやすくなるでしょう。
TikTok運用の目的別、インハウス化の向き不向き

TikTok運用は目的によって、インハウス運用が適しているか、外注が効果的かが大きく異なります。
下記の表で、主な目的ごとにインハウス向きか外注向きかを整理しました。
| 目的 | インハウス向き | 外注向き |
|---|---|---|
| 採用広報 | ◯ | △ |
| 商品PR | △ | ◯ |
| ブランディング | ◯ | ◯ |
このように、TikTok運用は目的ごとに最適な体制が異なります。
採用広報はインハウスが最適、商品PRは両方の強みを活かし、ブランディングはインハウスと外注のハイブリッド運用が理想です。
採用広報
採用広報はインハウス運用が最も効果を発揮します。
なぜなら、求職者が知りたいのは「どんな人が働いているか」「どんな雰囲気か」といったリアルな社内の様子だからです。
現場社員が自分の言葉で語ることで、求職者は「自分が働くイメージ」を持ちやすくなります。
そのため、日常の業務やオフィスの雰囲気を紹介する動画は、親近感や共感を生み、「この会社で働きたい」と思わせるきっかけになります。
外注の場合、映像のクオリティや編集力は高いものの、リアルな空気感や社員の熱量を表現しきれないことが多いでしょう。
採用広報はリアルさや共感性が最も重要なため、インハウス運用が最適です。
商品PR
商品PRはインハウスと外注の両方にメリットがあります。
自社の社員が商品知識や現場の声を活かして動画を作成すれば、ユーザーの疑問や興味に即座に応えられます。
開発担当者や現場スタッフが登場し、商品の特徴や使い方を紹介することで、説得力や信頼感が生まれます。
一方で、短期間で大量の動画を制作したい場合やインパクト重視のプロモーションを展開したい場合は外注が向いています。
プロのクリエイターによる演出や編集で、ブランドイメージの統一を図り、広告効果も高められます。
新商品発売やキャンペーン時には、外注のスピード感やクリエイティブ力が大きな武器になります。
そのため、日常的な発信はインハウス、大型施策は外注と使い分けるのが理想です。
ブランディング
ブランディング目的のTikTok運用は、インハウスと外注の両方で成果を出せます。
自社の価値観や世界観を一貫して伝えたい場合はインハウス運用が強みです。
社員自らがブランドの想いや日常のエピソードを発信することで、視聴者に「本物らしさ」や「共感」を与え、長期的なファンづくりにつながります。
一方、外注を活用すれば、ハイクオリティな映像や洗練された企画でブランドイメージを強化できます。
プロのクリエイターによる戦略的なキャンペーンや最新トレンドを取り入れた動画展開は、ブランドの認知拡大や新規層へのアプローチに有効です。
ブランディングでは、社内発信を続けつつ、必要に応じて外部の力も取り入れることで、より幅広い層にブランドの魅力を届けられます。
TikTok運用をインハウス化するメリット
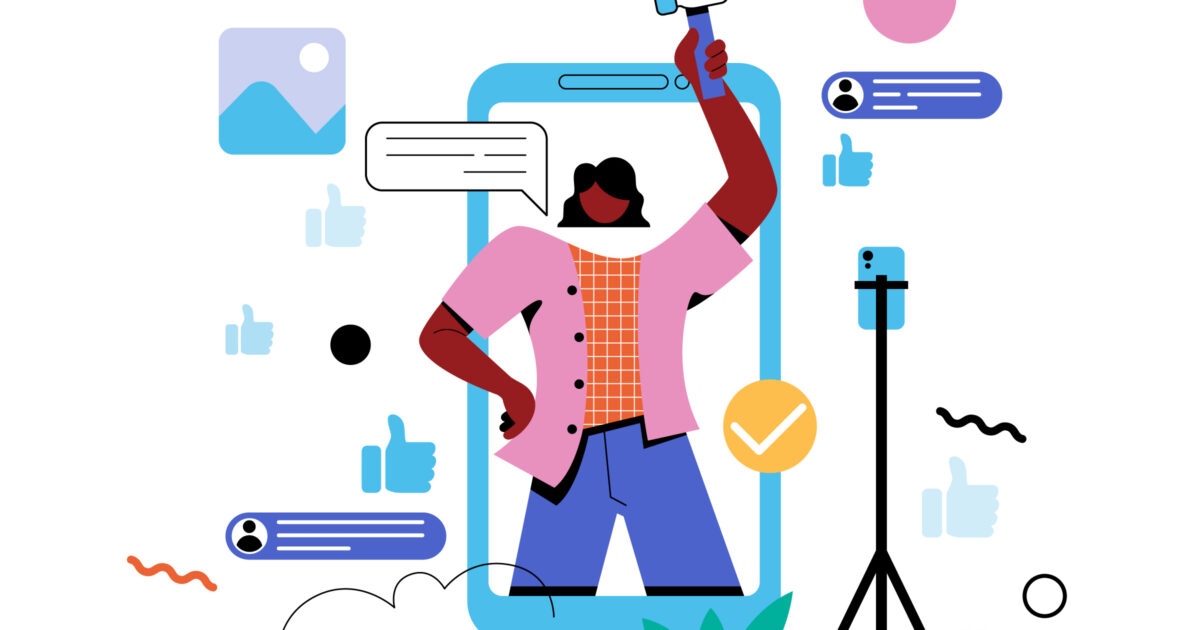
TikTok運用をインハウス化する最大のメリットは、企業独自の情報や現場感をそのまま伝えられる点です。
社内情報や業務知識を、そのまま動画コンテンツに転用できる
インハウス運用では、現場で働く社員が日々の業務や商品知識、サービスの裏側を自分の言葉で発信できます。
専門的な知見や現場ならではのノウハウをリアルタイムで動画に反映できるため、視聴者に「ここでしか聞けない話」を届けることが可能です。
外注では伝えきれない細かな現場の工夫や商品開発の裏話、業務のリアルな苦労ややりがいなど、企業独自の魅力をダイレクトに伝えられます。
また、社内にノウハウが蓄積されるため、PDCAサイクルを自社で高速に回しやすく、改善や新しいアイデアの実装も迅速です。
社内の感情・文化・リアルな熱量が可視化される
インハウス運用の大きな強みは、社員の表情や言葉、現場の空気感がそのまま映像に現れることです。
企業文化やチームの雰囲気、日常のやりとりなど、リアルな熱量が伝わることで、視聴者の「共感」や「親近感」を生みやすくなります。
たとえば、社内イベントや日常のちょっとした出来事を動画にすることで、企業の温かみや一体感が伝わりやすくなります。
こうしたリアルな発信は、採用やブランディングにも高い効果を発揮し、応募者やファンの増加につながることもあるでしょう。
TikTok運用が“組織の内部コミュニケーション”としても機能する
TikTok運用を社内で行うと、企画や撮影、編集を通じて社員同士のコミュニケーションが活発になります。
部署を超えたコラボレーションや若手社員のアイデアが活かされる場にもなり、組織全体の一体感や活性化につながります。
さらに、他部署の仕事内容や雰囲気を知るきっかけにもなり、社内SNS的な役割も果たします。
TikTok運用が社内のモチベーション向上やチームビルディングの機会にもなり得る点は大きな魅力です。
また、インハウス運用は外注と比べて運用コストを抑えやすく、手数料が発生しない分、予算を動画制作や広告配信に充てられるという経済的なメリットもあります。
TikTok運用をインハウス化するデメリット

インハウス化には独自性やリアルさという強みがある一方で、運用面での課題も少なくありません。
特にリソース確保や社内評価、他施策との連携が不十分だと、期待した成果につながりにくくなります。
社内での「TikTok担当」の立ち位置があいまいになりやすい
TikTok運用を兼任やボランティア的な役割で始めると、担当者の業務範囲や責任が不明確になりやすいです。
役割分担や評価指標が曖昧なままだと、誰がどこまで責任を持つのか分からず、運用が属人化しやすくなります。
また、担当者が異動や退職で変わるたびに運用方針が揺れたり、ノウハウが社内に定着しないまま失われるリスクも高まります。
こうした属人化を防ぐには、運用体制を明確にし、業務フローやマニュアルを整備したうえで、定期的な情報共有や引き継ぎを徹底することが重要です。
成果が定量化しにくく、社内評価に結びつきにくい
TikTokの運用成果は再生回数やエンゲージメント率などの定量的な指標が中心で、売上や採用数など直接的な成果に結びつきにくい傾向があります。
そのため、社内で評価基準が曖昧だと、「何となく投稿しているだけ」と見なされ、担当者のモチベーション低下にもつながります。
また、経営層や他部署に対して活動の意義や効果を説明しづらく、予算やリソースの確保も難しくなる場合もあるでしょう。
KPIや目標設定を明確にし、定期的に成果を可視化して振り返る仕組みを作ることが大切です。
TikTok以外の施策と統合しにくく、孤立しやすい
TikTok運用が単独で進行しやすく、他のマーケティング施策や広報活動と連動しづらい点もデメリットです。
全社的な戦略の中でTikTokの役割が明確でない場合、他部署との連携が生まれず、施策が孤立してしまいます。
キャンペーンや新商品の発表など、他チャネルと一体となった施策展開が難しくなり、全体最適が損なわれるリスクもあります。
こうした状況を防ぐには、TikTok運用を会社全体のマーケティングや広報戦略の一部として位置づけ、他部署と連携しやすい体制を整えることがポイントです。
インハウスと外注の比較

TikTok運用をインハウス化するか外注するかは、企業の目的やリソースによって最適解が異なります。
ここでは、主な比較ポイントを具体的に解説します。
| 比較項目 | インハウス運用 | 外注運用 |
|---|---|---|
| PDCA・改善サイクル |
・社内判断で即時対応しやすく、ノウハウが蓄積 ・現場の声をすぐ反映できる
|
・専門家の知見で効率的な改善
・最新トレンドや外部視点の活用がしやす |
| 運用コスト・ROI |
・人件費中心で長期的にROI向上しやすい ・コストパフォーマンスが高まる
|
・手数料が発生しやすい
・短期で成果を出しやすく即効性のある施策が可能 |
| 戦略設計・一貫性 |
・ブランド理解が深く、一貫性を保ちやすい ・企業独自の世界観やトーンを守れる
|
・多様な施策で幅広い展開が可能
・新規層へのアプローチも得意 |
社内PDCAと改善サイクルの回し方
インハウス運用の最大の強みは、現場の声や状況を即時に反映しやすい点です。
企画から投稿、分析、改善までを社内で一貫して進められるため、投稿後の反応をすぐにキャッチし、次の施策に素早く活かせます。
たとえば、視聴者のコメントやデータをもとに、その日のうちに動画内容や投稿タイミングを調整することも可能です。
こうした即時対応力は、トレンドの移り変わりが早いTikTokでは大きな武器となります。
また、社内でPDCAを回し続けることでノウハウが蓄積され、独自の成功パターンや改善策を自社で持てるようになります。
一方、外注の場合は、専門家やプロのクリエイターによる分析や改善提案が受けられるのが強みです。
最新のアルゴリズムやトレンドを踏まえた改善策を効率的に取り入れられますが、修正や意思決定には社内外の調整が必要となるため、スピード感がやや落ちることもあります。
外部とのやりとりが増えることで、細かなニュアンスの伝達や即時対応が難しくなる場合もあるため、運用フローの明確化が求められます。
特にトレンド変化への対応は、外注だとタイムラグが生じやすい点に注意が必要です。
運用コストとROI
インハウス運用は、主に人件費が中心となるため、長期的に見るとコストを抑えやすくなります。
外注手数料が発生しない分、予算を動画制作や広告配信に充てられるため、コストパフォーマンスが高まりやすいです。
さらに、社内にノウハウが蓄積されることで、運用の効率化や改善サイクルの高速化も期待できます。
特に、継続的な運用やブランド構築を目指す場合は、インハウスの方がROI(投資対効果)を高めやすい傾向があります。
一方、外注運用は短期間で成果を求める場合や、社内リソースが不足している場合に有効です。
プロのクリエイターや広告代理店に任せることで、短期間で高品質な動画や大規模なキャンペーンを展開できます。
ただし、制作費や運用手数料がかさみやすく、複数の施策を並行して進める場合はコストが膨らみやすい点に注意が必要です。
即効性や短期的な成果を重視する場合には外注が有利ですが、長期的なコスト管理や自社資産の蓄積という観点ではインハウスが有利です。
戦略設計と施策の一貫性
インハウス運用では、自社のブランドや価値観を深く理解したメンバーが企画から投稿まで一貫して携わるため、ブランドイメージやメッセージの統一がしやすいです。
企業独自の世界観やトーンを守りながら、長期的なファンづくりやブランド構築が可能になります。
現場のリアルな声や日常の空気感を反映しやすい点も、インハウスならではの強みです。
運用担当者が自社のビジョンや方針を理解しているため、細かな表現やニュアンスまで統一しやすく、ブランド価値を高める発信ができます。
外注の場合は、多様なノウハウや最新トレンドを取り入れやすく、幅広い施策展開が可能です。
プロの視点で新しい切り口やクリエイティブを提案してもらえるため、新規層へのアプローチや話題化を狙う場合に有効です。
ただし、複数の代理店や制作会社と関わる場合は、ブランドイメージやトーンの統一が難しくなることもあります。
外注先との連携やディレクションをしっかり行い、全体の一貫性を保つ工夫が必要です。
特に企業の世界観やブランドポリシーを外部パートナーと共有できていないと、発信内容にズレが生じやすくなるため、事前のすり合わせやガイドラインの整備が不可欠です。
インハウス運用でつまずく“よくある課題”と対策

TikTokのインハウス運用は、体制や仕組みが不十分なまま始めると継続や成果に結びつきません。
ここでは、現場でよく起こる課題と、その具体的な対策について解説します。
兼任チームで曖昧に始めると継続できない
TikTok運用を他業務と兼任でスタートすると、役割分担や責任範囲が曖昧になりやすいです。
誰かの善意や熱意に頼った運用は担当者の負担が増し、長続きしません。
そのため、専任担当者や明確なリーダーを決め、週次ミーティングなどで進捗や課題を共有する仕組みが不可欠です。
運用担当者が明確になれば、業務の属人化も防ぎやすくなります。
動画制作の属人化をどう防ぐか?
動画制作が特定の担当者に依存していると、その人が異動や退職した際に運用がストップするリスクが高まります。
ナレッジ共有やマニュアル化を徹底し、複数人で制作できる体制を整えることが重要です。
動画の企画・撮影・編集フローや投稿ルールを文書化し、誰でも参画できるようにしておくことで、急な人員変更にも柔軟に対応できます。
定期的な勉強会や情報交換の場を設け、ノウハウをチーム全体で蓄積していくことも大切です。
評価基準や改善ループがないと“なんとなく投稿”になる
KPIや明確な目標がないまま運用を続けると、成果が見えず、投稿自体が目的化してしまいます。
TikTokの特性に合わせて、再生回数やエンゲージメント率、フォロワー増加数など、数値で管理できる指標を設定しましょう。
週次や月次でデータを分析し、どの動画が伸びたか、どんな内容が反応を得られたかをチームで共有します。
改善点を具体的に洗い出し、次の投稿に反映させることで、運用の精度が高まります。
失敗しないためのインハウス運用体制のつくり方
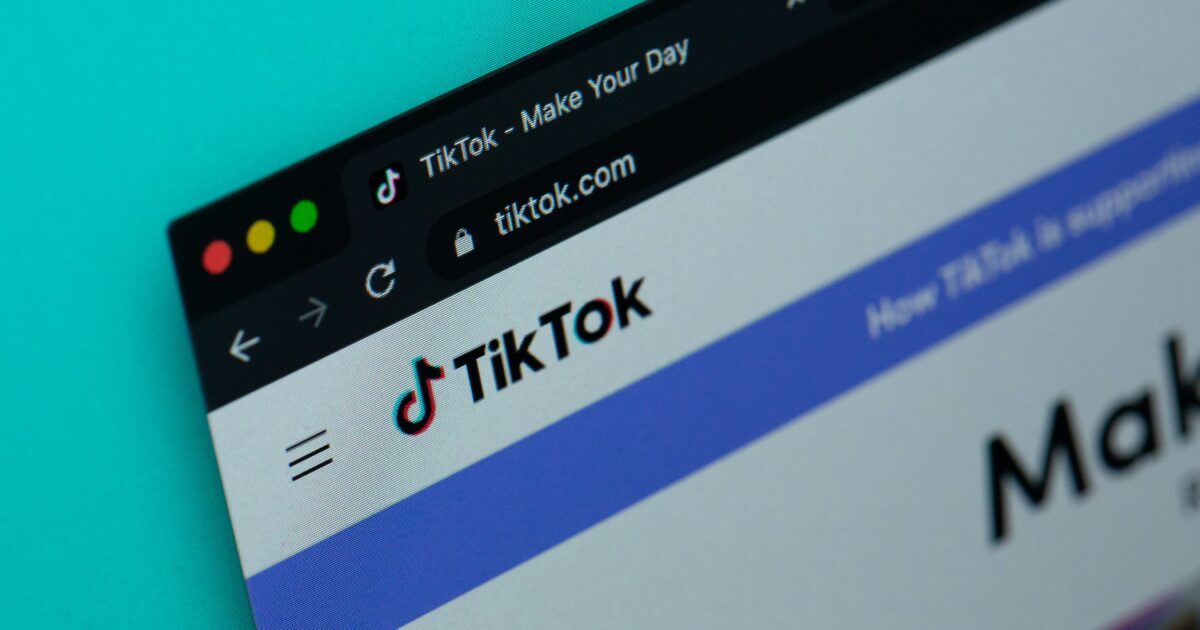
インハウスでTikTok運用を成功させるには、仕組み化と継続性の両立がポイントです。
誰が担当しても一定のクオリティを保てる体制を整えることで、安定した成果につながります。
兼任・小規模チームでも始められる仕組み化
大規模な専任チームがなくても、インハウス運用は十分にスタートできます。
小規模チームの場合は、最初に役割分担と運用ルールを明確に決めることが重要です。
たとえば、企画・撮影・編集・投稿などの業務を担当者ごとに割り振り、無理のない範囲でタスクを進められるようにします。
業務の属人化を防ぐためにも、業務フローや手順を共有し、誰が抜けても運用が止まらない体制を目指しましょう。
小さなチームでも、仕組みさえ整えば安定した運用が実現できます。
PDCAを回すための週次ルーティンとKPI設定
成果を出すためには、PDCAサイクルを回す仕組みも必要です。
毎週の定例ミーティングや進捗共有を行い、運用状況をチーム全体で確認します。
再生回数やエンゲージメント率、フォロワー数など、目的に応じたKPIを設定し、週ごとに目標の達成度をチェックしましょう。
データをもとに改善点を話し合い、次の施策に反映させることで、運用の精度が高まります。
KPIが明確になることで、担当者のモチベーション維持や成果の可視化にもつながります。
再現性のある運用体制とトレンド対応力の両立
安定した運用には、再現性の高い体制づくりが欠かせません。
運用マニュアルや動画制作フローを整備し、誰でも一定のクオリティで投稿できる状態を目指しましょう。
同時に、TikTokはトレンドの変化が激しいため、柔軟な対応力も必要です。
トレンド分析や競合調査を定期的に行い、最新の話題やアルゴリズムの変化をキャッチアップしてください。
マニュアルと柔軟性を両立させることで、安定感と成長力を兼ね備えた運用体制が実現します。
インハウス化を成功に導く、デジマケスクール&トレーナー

TikTok運用のインハウス化を成功させるには、専門的な知識やノウハウの習得が必要です。
自社だけでノウハウを蓄積するのが難しい場合、外部の教育サービスを活用しましょう。
デジマケスクール

デジマケスクールは、TikTok運用の基礎から応用まで、実践的なプログラムを提供しています。
初心者でも安心して学べる内容で、広告代理店レベルのスキルを短期間で習得できます。
月額制で気軽に始められるため、インハウス担当者の育成やスキルアップに最適です。
現場で役立つノウハウや最新トレンドも学べるため、即戦力として活躍できる人材を育てられます。
デジマケトレーナー

デジマケトレーナーは、現場での実践を重視したマンツーマンサポートが特徴です。
自社の課題や目標に合わせて、プロのトレーナーが運用体制の構築や改善を直接支援します。
自走できるチームづくりや最新トレンドへの対応力強化にも役立ちます。
個別の課題解決や、継続的なサポートを受けることで、インハウス運用の成功率が高まります。
まとめ
TikTok運用のインハウス化は、企業のリアルな魅力や文化を直接伝えるために有効です。
現場の熱量や共感をダイレクトに届けることで、ブランドの信頼やファン獲得につながります。
一方で、体制や評価基準を整えないと継続や成果が難しくなるため、仕組み化とスキルアップが不可欠です。
自社に合った運用体制を構築し、TikTokの特性を最大限に活かしましょう。
デジタルトレンズへお気軽にご相談下さい。