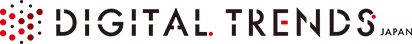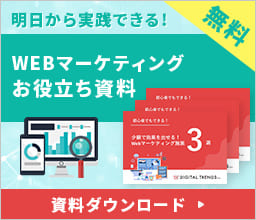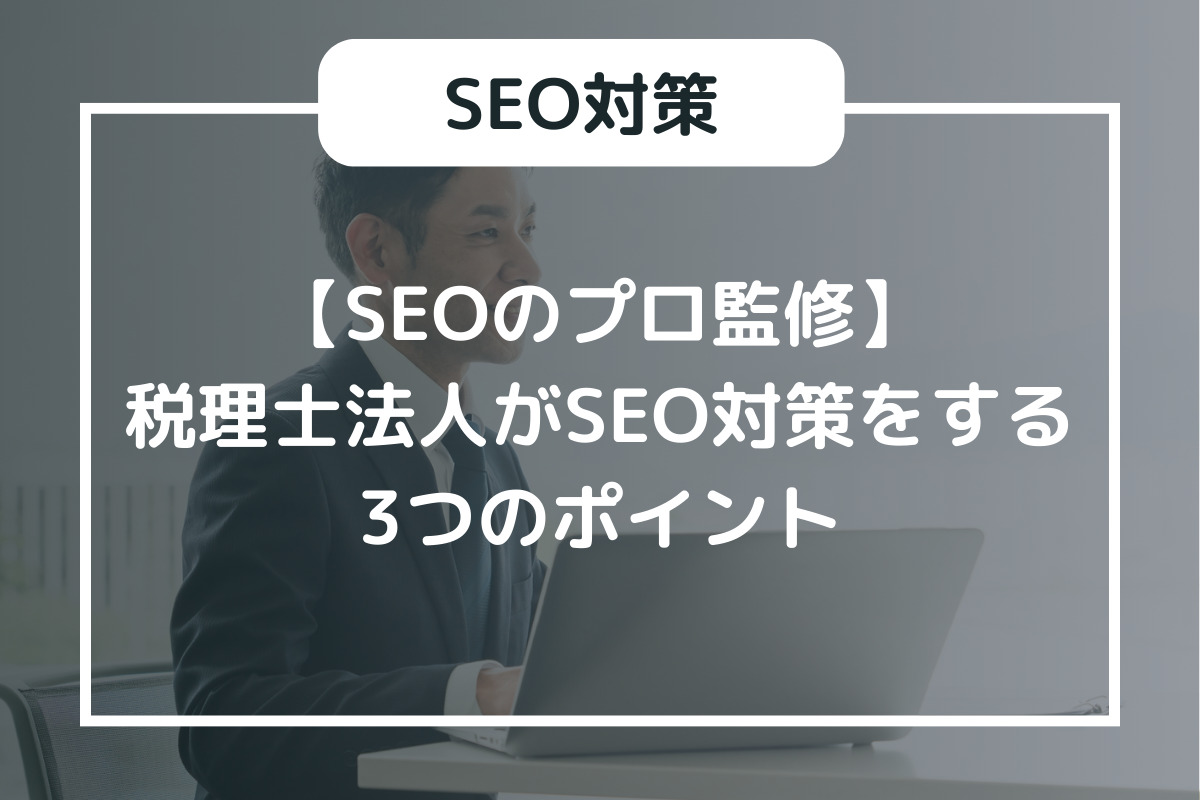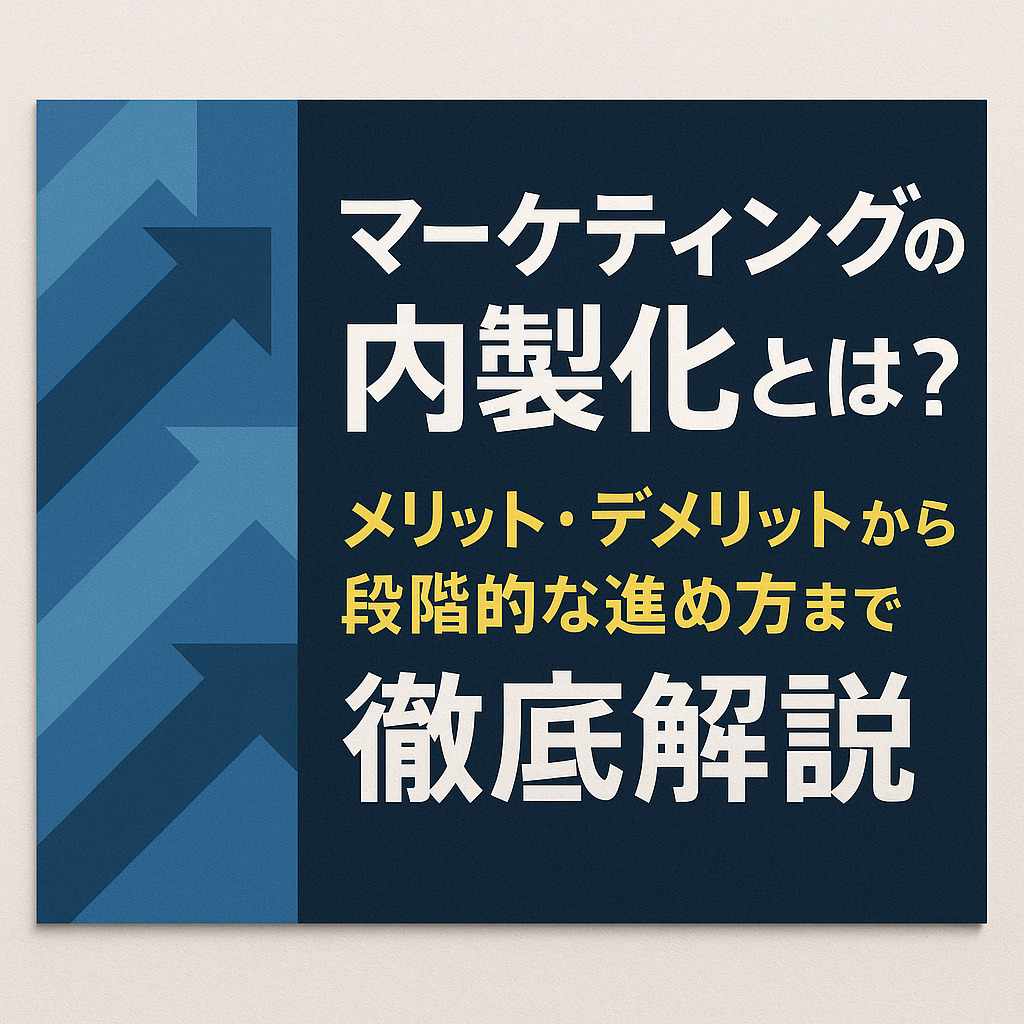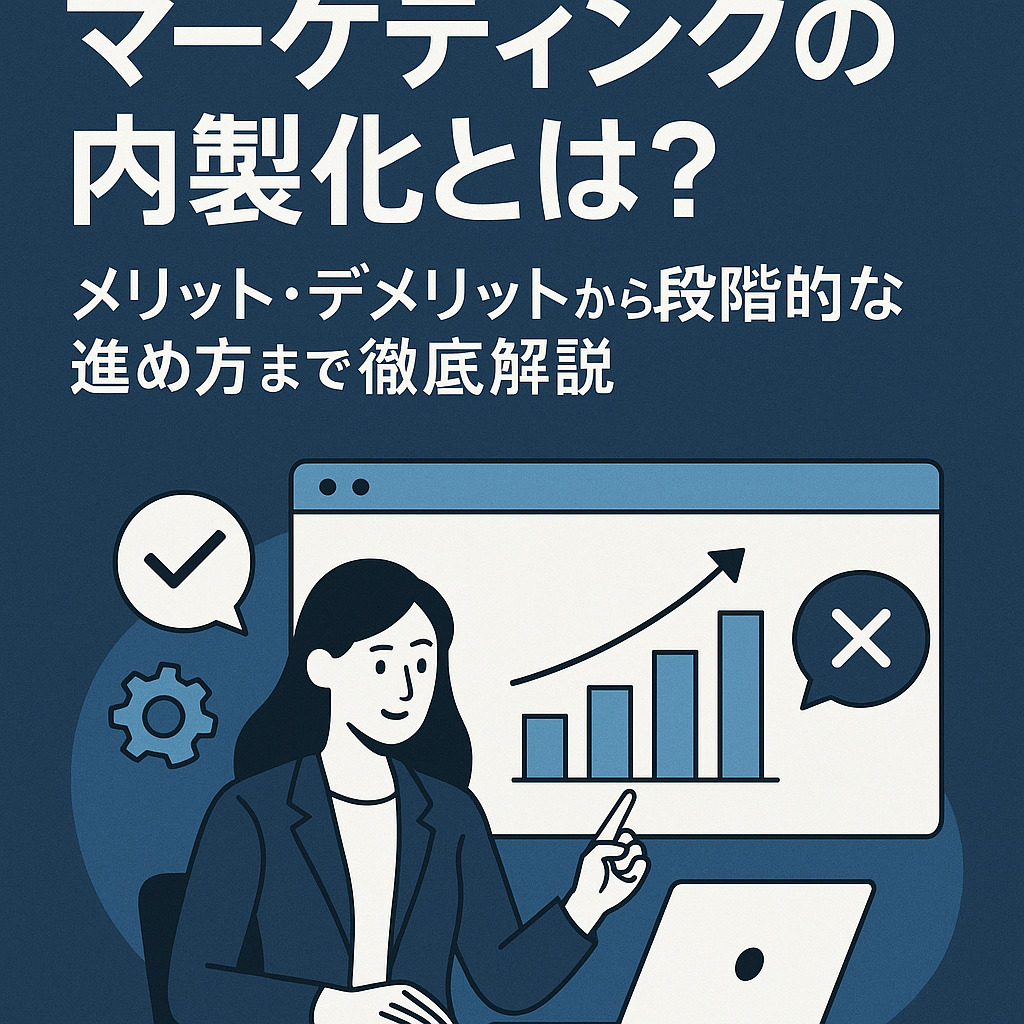オウンドメディアの構築・運用と費用を徹底解説


目次
オウンドメディアの運用代行にかかる費用
まず初めに、オウンドメディアの運用代行にかかる費用の目安を確認しておきましょう。
支援項目とそれぞれの費用の目安について下記にまとめました。
【オウンドメディアの運用代行にかかる費用の目安】
| 項目 | 運用代行費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 記事制作 | 1万~10万円程度/1記事 | コンテンツの種類やボリュームによって異なる。 |
| 動画制作 | 10~50万円程度/1動画 | コンテンツの種類やボリュームによって異なる。 |
| 内部対策支援 | 10~100万円程度/1サイト | 検索エンジンにサイトの内容を適切に伝えるために内部構造を最適化させる。
サイトの種類や規模により大きく異なる。 |
| SEOコンサルティング | 10万円~/月 | 実行部分は自社で行い、サイト運営の方向性などをサポートする。(実行部分も依頼できる場合がある) |
これらの費用はあくまでも目安です。
実際の費用は、代行業者やサイト規模によって大きく変化します。
オウンドメディアの構築・運用の費用相場
オウンドメディアの設計・外注にかかる費用はどれくらいなのでしょうか?オウンドメディアを製作する時に、一番気になるのが費用です。
こちらでは、自社で設計から運用する場合と外注した場合の費用について、それぞれの相場を紹介します。
自社で設計から運用する場合の費用
自社で設計・構築・運用する場合の費用の相場は、おおよそ〜150万円ほどかかります。
ドメイン取得費:~2,000円
レンタルサーバー費:10,000~30,000円前後
CMS構築費:10〜30万円
コンテンツ制作費:5~10万円
マーケティング・解析・改善費:50~90万円
運用:10~20万円
自社で専門的知識を持つエンジニアやライターを継続して雇用するには、雇用単価が高くなります。
外注した場合の費用
外注した場合の費用は、おおよそ〜300万円ほどかかります。
設計・構築・運用までの基本費用:100~150万円
営業・ディレクション・諸経費:100~150万円
外注して設計・構築・運用すると〜300万円かかりますが、運用に入ると専門的知識を持つエンジニアやライターを外注できるので、自社運用する場合と比較すると安く済ませることができます。
オウンドメディアの立ち上げ・運用は外注もできる
オウンドメディアの作り方の中には、自社運用をするか外注化するかも決めなければいけません。それぞれのメリットとデメリットを解説します。
外注化のメリット・デメリット
次に外注化のメリットは、クオリティの高いオウンドメディアを作れる点です。
今まで複数のオウンドメディアを運用し、成果を出している制作会社に外注すれば、集客面での不安は少なくなります。
指示を出すだけで作業を全て請け負ってもらえる点も外注化の魅力です。
一方のデメリットですが、コストが高くなる点です。基本的にはメディア事業を手掛ける「プロ」に依頼することになるので、それだけ費用がかかることがあります。
自社運用、外注化した際のメリット・デメリットをまとめると以下になります。
自社運用のメリット・デメリット
まず、自社運用ですが、一番のメリットは運用コストが低い点です。
社内で管理することで、コストを抑えつつ連携を取りやすくなります。
社内でオウンドメディアを運用できる人材がいれば、自社運用を検討の余地があるでしょう。
一方の自社運用のデメリットですが、オウンドメディアのプロではないのでクオリティが低くなり、全く集客ができないという可能性も十分にあります。
オウンドメディアの運用は、ただ記事をアップしていけば良いわけではないので、そのあたりの判断は慎重に行うべきでしょう。
デジタルトレンズへお気軽にご相談下さい。
オウンドメディアの運用、制作をご検討の方へ
通常は複数の部署や中間会社を経て提供されているものがほとんどですが、弊社、株式会社デジタルトレンズでは一人ひとりが運用から分析、提案までサポート致します。
常に変化している市場に合わせて”生きた施策”を実践することができるのが強みです。
Webマーケティングやホームページ制作でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
デジタルトレンズへお気軽にご相談下さい。
【代理店選定が9割】失敗しない広告代理店探しのポイント6選!
.jpg)
「自社に最適な代理店がわからない」「インハウス運用か代理店依頼かで悩んでいる」そんな企業様に向けて、失敗しない広告代理店の探し方についてまとめ資料になります。
今すぐ資料を無料ダウンロード