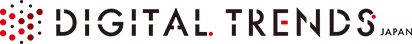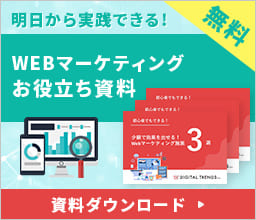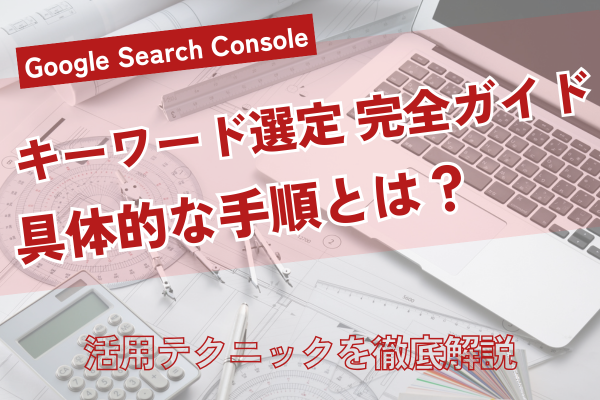インハウスマーケティングとは?メリット・デメリットから成功事例まで徹底解説
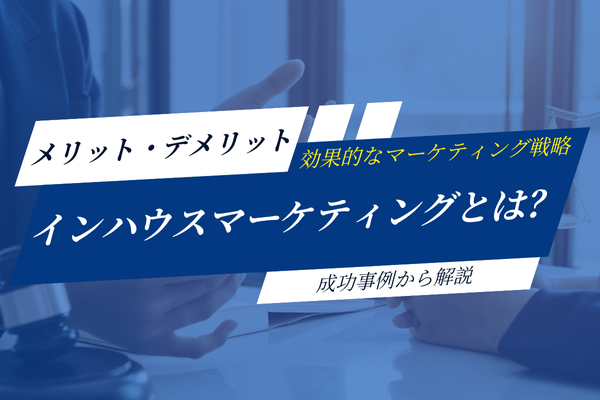
企業が競争力を維持するためには、効果的なマーケティング戦略が欠かせません。
しかし、外部の広告代理店に依頼することで、コストがかさむうえに、自社のノウハウが蓄積されないという悩みを抱えている企業も多いでしょう。
そこで注目されているのがインハウスマーケティングです。
本記事では、インハウスマーケティングの基本からメリット・デメリット、成功に向けた具体的なステップまで解説します。
インハウスマーケティングとは

インハウスマーケティングとは、企業が自社内でマーケティング活動を行う手法を指します。
また、インハウスマーケティングでは、デジタル広告やSEO対策などのオンライン施策がインハウス化しやすいです。
これらは社内で管理が可能で、比較的少ないコストで実施できます。
一方、テレビCMや新聞広告などのオフライン広告は、広告代理店のネットワークを必要とするため、インハウス化が難しい領域です。
また、専門的なクリエイティブ制作も外部の専門家に依頼することが多いでしょう。
インハウスマーケティングのメリット
ここからは、インハウスマーケティングのメリットをご紹介します。

ノウハウとデータが社内に蓄積する
インハウスマーケティングの最大のメリットは、マーケティングのノウハウとデータが社内に蓄積されることです。
外部に委託していた時代には、貴重な情報が社外に流出していました。
しかし、自社で運用することで、全てのデータを自社で管理できるようになります。
その結果、過去の施策の成功や失敗の要因を深く分析できるようになるでしょう。
また、社員がマーケティングスキルを磨くことで、会社全体の競争力が高まります。
日々の業務を通じて、社員一人ひとりがマーケティングの知識を蓄積していきます。
この経験は、将来的に会社の大きな財産となるでしょう。
コスト削減につながる
インハウスマーケティングは、長期的に見るとコスト削減につながります。
外部の広告代理店に依頼する場合、高額な手数料がかかることがあります。
しかし、自社で運用すれば、その分のコストを抑えられます。
インハウス化しても初期投資は必要ですが、時間とともにコストパフォーマンスは向上していきます。
特にデジタルマーケティングの分野では、ツールの導入や人材育成にかかる費用を考慮しても、長期的には大幅なコスト削減が期待できるでしょう。
業務効率化につながる
インハウスマーケティングは、業務の効率化にも貢献します。
外部に委託する場合、コミュニケーションの行き違いや意思決定の遅れが生じることがあります。
しかし、社内で完結すれば、スピーディーな対応が可能です。
また、マーケティング部門と他の部門との連携も円滑になります。
たとえば、営業部門との情報共有がスムーズになり、顧客ニーズにより迅速に対応できるようになるでしょう。
この相乗効果により、会社全体の生産性が向上します。
自社商品・自社顧客への深い理解ができる
インハウスマーケティングの強みは、自社の商品や顧客を深く理解できる点です。
外部の代理店は複数の顧客を抱えているため、一社に集中することが難しいです。
しかし、自社のマーケティングチームは、常に自社製品と向き合っています。
この深い理解は、より効果的なマーケティング戦略の立案につながります。
顧客の声を直接聞き、製品開発にフィードバックすることも可能です。
結果として、顧客満足度の向上や、より魅力的な商品開発につながるでしょう。
インハウスマーケティングのデメリット
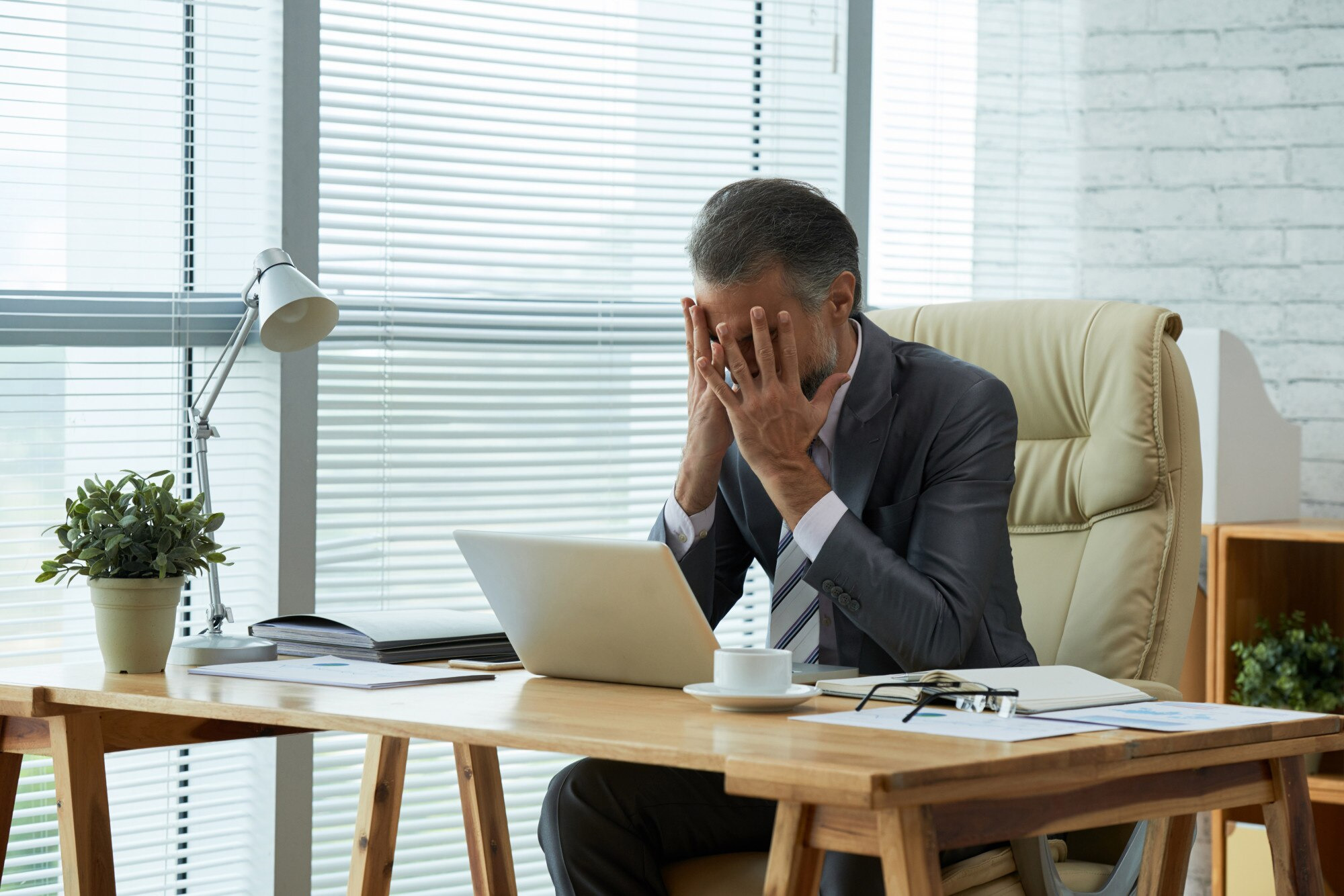
インハウスマーケティングには多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。
ここからは、インハウスマーケティングを導入する際に注意すべき主な課題について解説します。
専門人材の確保や育成が難しい
インハウスマーケティングの大きな課題は、専門人材の確保と育成です。
マーケティングの世界は日々進化しており、最新のスキルや知識を持つ人材を見つけるのは容易ではありません。
特にデジタルマーケティングの分野では、技術の進歩が著しく、常に新しい知識が求められます。
この課題に対しては、計画的な人材育成が重要です。
社内研修の充実や外部セミナーへの参加を積極的に推奨しましょう。
また、経験豊富な人材をヘッドハンティングすることも一案です。
業務の属人化につながる場合がある
インハウスマーケティングを進めると、特定の個人に業務が集中しがちです。
これは「属人化」と呼ばれ、組織にとって大きなリスクとなります。
たとえば、キーパーソンが突然退職した場合、業務が滞る可能性があります。
この問題を解決するには、業務の標準化とマニュアル化が欠かせません。
個人の暗黙知を形式知に変換し、誰でも同じレベルの業務ができるよう整備しましょう。
また、複数の人員でスキルを共有する「クロストレーニング」を取り入れると、特定の個人に依存しない強固な組織体制を築けます。
外部視点や最新トレンドの取り込みにくさがある
インハウスマーケティングの弱点として、外部の新しい視点や最新トレンドを取り入れにくいことが挙げられます。
同じメンバーで長期間業務を行うと、思考が固定化してしまう恐れがあります。
これは、創造性や革新性の低下につながるでしょう。
この課題を克服するには、外部との接点を意識的に増やす必要があります。
業界のカンファレンスや展示会に積極的に参加し、最新情報をキャッチアップしましょう。
また、外部のコンサルタントを定期的に招いて、新鮮な視点を取り入れるのも良いでしょう。
さらに、社内でブレインストーミングセッションを開催し、自由な発想を促すことも大切です。
異なる部署のメンバーを交えることで、多様な視点が生まれます。
インハウスマーケティングを成功させるためのポイント

ここでは、効果的にインハウスマーケティングを進めるための5つのポイントを紹介します。
これらのポイントを理解し、実践することで、企業のマーケティング活動をより強固なものにできます。
段階的にインハウス化を進める
インハウスマーケティングは、一度に全てを社内で行う必要はありません。
段階的に進めることで、リスクを最小限に抑えつつ、スムーズに移行できます。
まずは、デジタル広告やソーシャルメディア運用など、比較的管理しやすい業務から始めましょう。
そうすると、初期段階での成功体験を積み重ねることができます。
その後、徐々に他のマーケティング活動も社内で行うようにします。
このプロセスでは、各段階での成果を評価し、必要に応じて調整を加えることが重要です。
こうした段階的なアプローチは、組織全体の負担を軽減し、持続可能な成長につながります。
社内体制の整備と人材育成を行う
インハウスマーケティングを成功させるためには、社内体制の整備と人材育成が欠かせません。
まずは、明確な役割分担と責任範囲を設定しましょう。
これにより、各メンバーが自分の役割を理解し、効率的に業務を遂行できます。
また、先述のとおり、人材育成にも力を入れる必要があります。
社員が最新のマーケティング手法やツールを習得できるように、定期的な研修やセミナー参加を促進しましょう。
データ分析とPDCAサイクルを確立する
データ分析とPDCAサイクルの確立は、インハウスマーケティングの成功に不可欠です。
まずは自社で収集したデータを活用し、市場や顧客の動向を把握しましょう。
この情報は、戦略立案や施策改善に役立ちます。
さらに、PDCAサイクルを導入することで、継続的な改善が可能になります。
計画した施策を実行し、その結果を評価して改善策を講じるという流れです。
このプロセスを繰り返すことで、マーケティング活動の精度が向上し、より効果的な施策が実現します。
外部パートナーと連携する
インハウスマーケティングとはいえ、全てを自社だけで完結させる必要はありません。
外部パートナーとの連携もポイントです。
特に自社で対応できない専門的な業務や最新トレンドの取り込みには外部の力が役立ちます。
たとえば、新しい技術や市場動向については専門家からアドバイスを受けることで、自社の視野を広げられます。
また、一時的なリソース不足には外部委託も検討しましょう。
このように柔軟な連携体制を築くことで、自社の強みと外部リソースを最大限活用できます。
インハウスマーケティングの導入ステップ
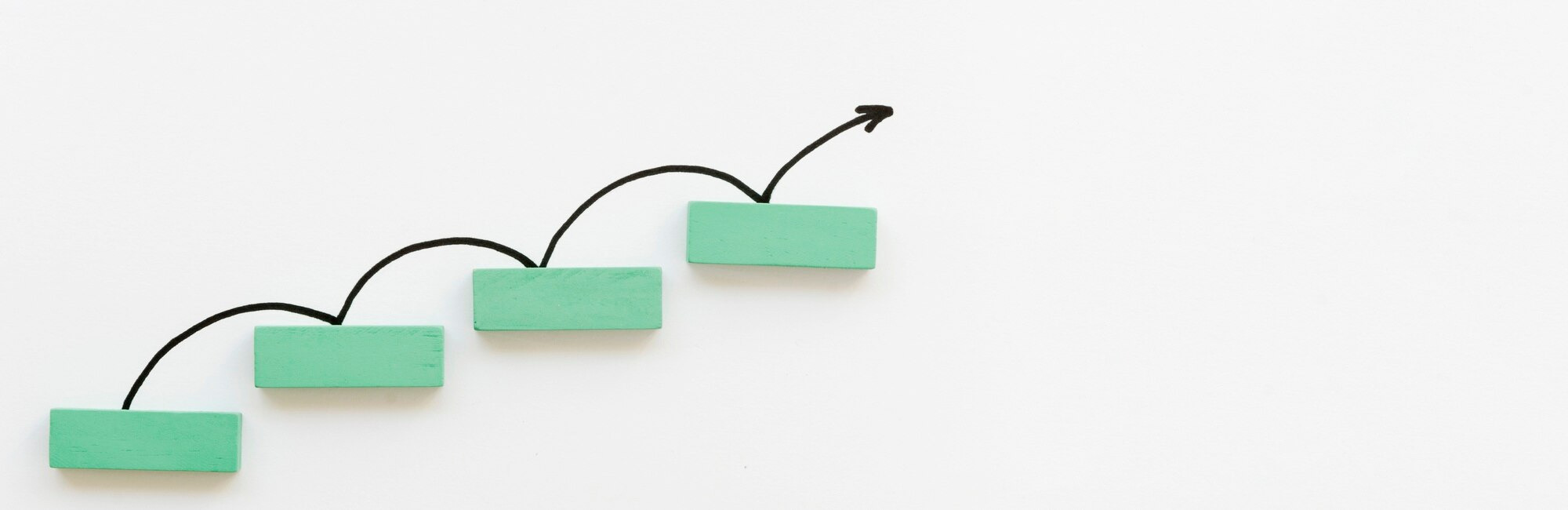
インハウスマーケティングの導入は、計画的に進めることがポイントです。
ここでは、効果的な導入のための5つのステップを解説します。
これらのステップを順に踏むことで、スムーズにインハウスマーケティングを始められるでしょう。
現状分析から目標を設定する
まずは、自社のマーケティング活動の現状を正確に把握しましょう。
外部に委託している業務の内容や費用、その効果を細かく分析します。
また、社内のマーケティングスキルや人員配置の状況も確認してください。
この分析結果をもとに、インハウスマーケティングの目標を設定します。
たとえば、「1年後にデジタル広告運用を完全に内製化する」といった具体的な目標を立てます。
目標は数値化し、達成時期を明確にすることが大切です。
インハウス化する業務を選定する
次に、どの業務をインハウス化するか選定します。
全ての業務を一度にインハウス化するのは難しいため、優先順位をつけましょう。
たとえば、SNS運用やコンテンツマーケティングなど、比較的取り組みやすい業務から始めるのがおすすめです。
選定の際は、自社のリソースと業務の難易度のバランスを考慮してください。
また、インハウス化による効果が大きい業務を優先的に選ぶと良いでしょう。
コスト削減や効率化が見込める業務から着手することで、早期に成果を実感できます。
必要なスキルとリソースを洗い出す
選定した業務をインハウス化するために、必要なスキルとリソースを明確にします。
たとえば、デジタル広告運用ならば、広告プラットフォームの操作スキルや分析力が求められます。
また、必要なツールや予算も洗い出しましょう。
人材面では、既存の社員のスキルアップで対応できるか、新規採用が必要かを判断します。
場合によっては、外部の専門家による研修も検討しましょう。
リソースの洗い出しは綿密に行い、不足している部分を明確にすることが大切です。
ロードマップを作成する
インハウス化の全体像を把握するために、詳細なロードマップを作成しましょう。
これは、目標達成までの道筋を時系列で示したものです。
各業務のインハウス化の時期、必要なリソースの調達タイミング、人材育成のスケジュールなどを盛り込みます。
また、ロードマップには、中間目標や評価のタイミングも設定しましょう。
そうすれば、進捗状況を確認しながら、必要に応じて計画を修正できます。
柔軟性を持たせることで、予期せぬ事態にも対応できるロードマップになるでしょう。
段階的に実施する
最後に作成したロードマップに沿って、段階的にインハウス化を進めます。
一度にすべてを変更するのではなく、小さな成功を積み重ねていく方法が効果的です。
たとえば、最初の3ヶ月はSNS運用のみをインハウス化し、その後デジタル広告に着手するといった具合です。
そして、各段階で成果を評価し、必要に応じて計画を調整します。
うまくいかない部分があれば、原因を分析し改善策を講じます。
また、成功事例は社内で共有し、モチベーション向上につなげましょう。
インハウスの勉強ならデジマケスクール

マーケティングでのインハウス運用を目指す方には「デジマケスクール」がおすすめです。
「デジマケスクール」では、第一線で活躍する現役Webマーケターが設計し、マーケティングの知識とスキルを効果的に身につけられます。
初心者の方でも短期間でプロのレベルへ到達できるよう、1動画15分の効率的な学習スタイルを採用しています。月額2,980円という始めやすい価格で、コストを抑えながら本物のスキルを手に入れることができます。
企業内での広告運用体制構築や個人のスキルアップに最適なので、ぜひ受講してみてください。
プロの伴走支援で”成果に繋がる”インハウス運用へ

「とりあえず運用しているが、成果に繋がっているか自信がない」。
そんな現場担当者の悩みに「デジマケトレーナー」は応えます。
デジマケトレーナーは、月額2980円から利用できるプロの伴走支援が、日々の業務を「正しい方向」に導きます。
効果測定の正しい方法、データに基づいた改善案の出し方など、成果に直結するノウハウを指導します。
感覚的な運用から脱却し、自信を持って施策を進められるようになります。
まとめ
インハウスマーケティングは、自社内でノウハウを蓄積し、コスト削減や業務効率化を図るための有効な手段です。
本記事で紹介したステップを踏むことで、段階的にインハウス化を進め、成功に近づくことができます。
専門人材の育成や外部視点の取り込みといった課題もありますが、それらを克服するための方法もあります。
自社の状況に合わせて柔軟に対応しながら、新しいマーケティング体制を構築してみましょう。
デジタルトレンズへお気軽にご相談下さい。