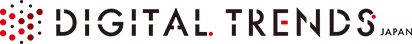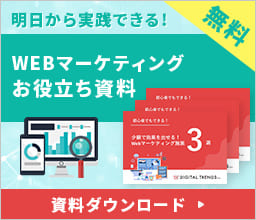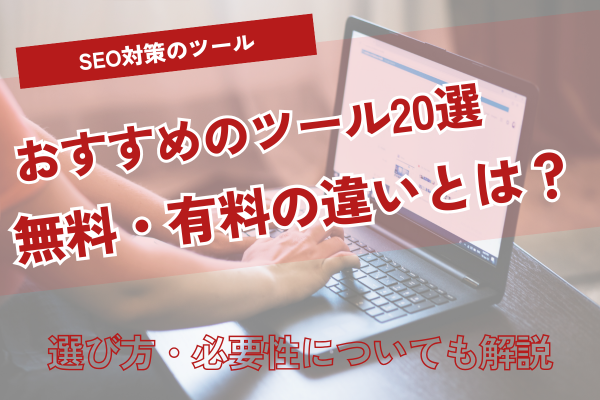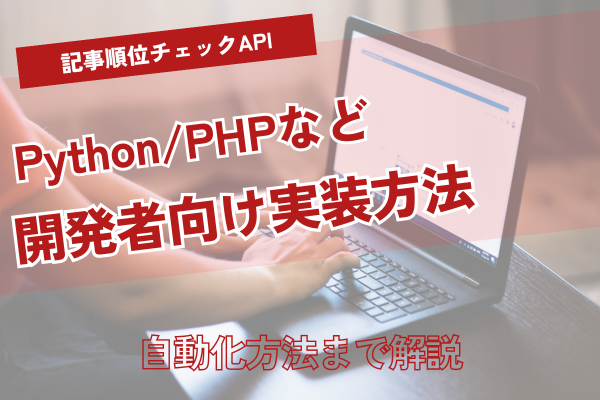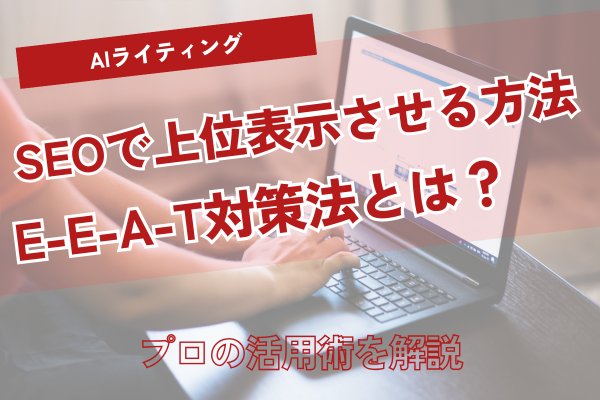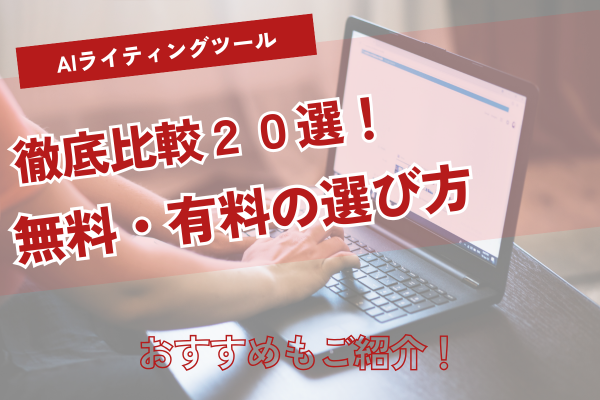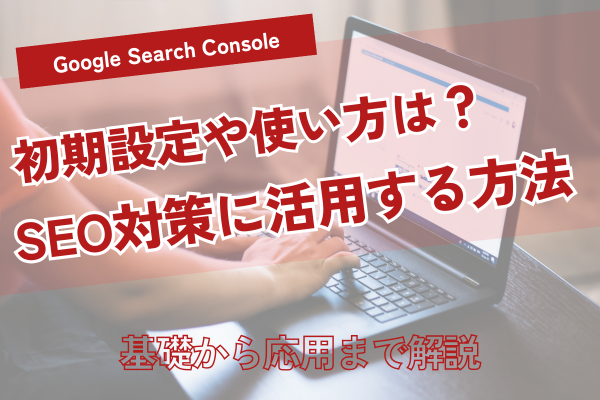インハウスでディスプレイ広告を運用するメリット・デメリット、導入検討時の注意点などを詳しく解説
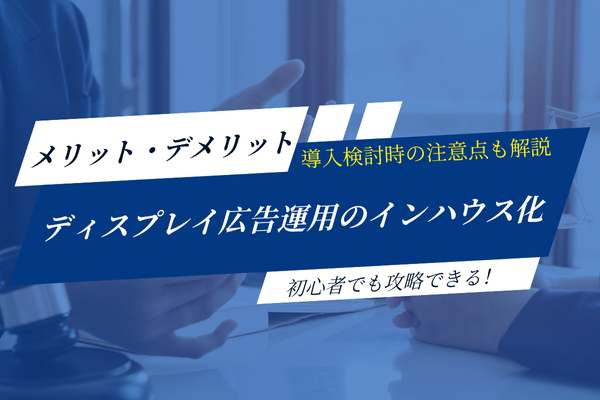
ディスプレイ広告のインハウス化は、企業が広告運用を自社内で行うことで多くのメリットを得られます。
しかし、運用負担も増えるため、自社のリソースにあわせた体制を整える点も大切です。
本記事ではインハウス化を検討する際に知っておくべきメリット・デメリット、成功のポイント、具体的な移行ステップを解説します。
これからディスプレイ広告のインハウス化を進めたい場合は、ぜひ参考にしてください。
ディスプレイ広告をインハウス化をするメリット

ディスプレイ広告のインハウス化は、企業にとって多くのメリットを得られる手法です。
具体的なメリットを3つの観点から解説します。
運用代行手数料がコストカットできる
インハウス化の大きなメリットは、広告代理店に支払う手数料を削減できる点です。
通常、広告代理店を利用すると広告費用の一定割合(一般的に15〜20%)が手数料として発生します。
この費用は、中小企業や広告予算が限られている企業にとって大きな負担となるものです
しかし、インハウス化することで、この手数料を削減し、その分の予算を広告出稿や他のマーケティング施策に再配分できます。
たとえば、広告費100万円のうち20%が手数料として差し引かれる場合、インハウス化によって20万円を節約し、その金額を新たな施策に投入できるわけです。
このように、コスト効率を高められる点は、企業全体の利益率向上にも好影響です。
広告運用の知識・ノウハウを社内に蓄積できる
インハウス化は単なるコスト削減だけでなく、長期的な視点で見れば「知識とノウハウの蓄積」という企業にとって大きな資産をもたらします。
代理店に依存している場合、その知識や運用技術は外部に留まり、自社には蓄積されません。
一方で、自社内で運用を行うことで、社員が運用スキルや市場動向への理解を深めることができます。
また、この知識は組織全体で共有されるため、新しいメンバーへの教育や他部署への展開も容易になります。
たとえば、データ分析やターゲティング技術などの専門知識は、マーケティング全体の戦略強化にもつながります。
さらに、こうしたノウハウが蓄積されることで、広告運用だけでなく商品開発や顧客対応に活かすことも可能です。
業務やリソースを自社内で調整し、迅速な意思決定が可能
インハウス化によって、自社内で業務フローやリソース配分を柔軟に調整できるようになります。
代理店を利用している場合には、意思決定には複数のステップが必要となり、その分対応が遅れることがあります。
しかし、自社で運用する場合は、リアルタイムで市場データや顧客フィードバックを反映しながら迅速に施策を変更できます。
たとえば、新商品のプロモーション時に急遽ターゲティング設定やクリエイティブ内容を変更したい場合でも、自社運用なら即座に対応可能です。
また、自社内で意思決定プロセスが完結するため、透明性も向上し、不必要なコミュニケーションロスも防げます。
ディスプレイ広告をインハウス化をするデメリット

ディスプレイ広告のインハウス化には多くのメリットがありますが、同時にいくつかの課題も伴います。
以下では、代表的なデメリットについて具体的に解説します。
運用負担が増える
インハウス化を進めると、広告運用に関する業務量の増加が大きな課題です。
代理店に依頼していると、運用や分析、改善提案などをすべて任せられるものの、自社で運用する場合は、それらの作業を社員が担う必要があります。
特に広告運用にはデータ分析やターゲティング設定など、高度な専門知識が求められるため、習得するためには時間と労力が必要です。
また、日々の運用業務に加え、トラブル対応や新しい施策の立案なども発生します。
さまざまな業務負担が増えることで、ほかの業務に支障が出る可能性も考えられるでしょう。
広告代理店向けのツール制限による競争力の低下
広告代理店は、専用の高機能なツールやプラットフォームを利用している場合が多いです。
それらのツールは、高度な最適化機能や効率的なデータ分析機能を備えており、広告運用の質を高めるために役立っています。
一方で、自社で運用を行う場合は、それらのツールを利用できないケースがあります。
そのため、代理店と比較して運用効率や精度で劣ることも考えられます。
たとえば、大量のキャンペーン管理や高度な自動化機能が必要なときに自社内で対応しきれないこともあるでしょう。
このようなツール制限は、競争力低下につながります。
Googleなどの媒体担当者から情報をキャッチアップできない
広告代理店は、GoogleやFacebookなど主要な広告媒体とのコネクションを持っています。
そのため、新しい機能やアルゴリズム変更などの最新情報をいち早く入手し、それを活用した提案を行うことが可能です。
一方で、自社運用の場合はこうした情報源へのアクセスが限られることがあります。
そして、媒体担当者から直接サポートを受けられないため、新しい施策への対応が遅れる可能性があります。
また、市場動向や競合状況についても十分な情報収集が難しいこともあるでしょう。
この情報格差は、広告運用の成果に影響する要因となり得ます。
バナーの制作スキルが求められる
ディスプレイ広告では、バナーの質が成果に直結します。
特にターゲット層に刺さるデザインやコピーライティングには経験とセンスが必要です。
そのため、デザイナーやコピーライターなど専門職の採用や育成が求められるでしょう。
また、制作リソース不足によって品質が低下したり納期遅延が発生したりする点も注意が必要です。
インハウス化への移行を検討するタイミング

ディスプレイ広告のインハウス化は、適切なタイミングで実施することがポイントです。
ここからは、移行を検討すべき具体的な状況について解説します。
費用に対して代理店運用で成果が見込めないとき
代理店に運用を依頼すると、広告費に加えて手数料が発生します。
手数料を支払っても十分な利益を確保できれば問題ないでしょう。
しかし、その費用に見合った成果が得られていない場合は、インハウス化を検討するタイミングです。
たとえば、クリック単価やコンバージョン率が期待値を下回っているときには、自社で運用を見直すことでコストパフォーマンスを向上させられる可能性があります。
外注して目標とする数値が得られない場合は、自社で取り組めないかを検討しましょう。
社内にノウハウを蓄積したいとき
長期的な視点でマーケティング力を強化したいときは、インハウス化が有効です。
なぜなら、外部に依存していると運用ノウハウやデータ分析の知識が社内に蓄積されないからです。
たとえば、新たな広告プラットフォームやターゲティング技術の導入時にも自社内の知識基盤があれば迅速に対応できます。
また、このノウハウは他のマーケティング施策にも応用でき、企業全体の利益にも好影響です。
人的リソースがあるとき
広告運用にはデータ分析やクリエイティブ制作など、多岐にわたる業務があり、インハウス化の際は十分な人的リソースが必要です。
たとえば、マーケティング部門にデジタル広告の経験者がいる場合や新たに専門人材を採用できる余裕がある場合は、インハウス化によるメリットが大きいでしょう。
ディスプレイ広告のインハウス化を成功させるポイント

ディスプレイ広告のインハウス化を成功させるためには、計画的な準備と適切な運用が欠かせません。
そこで、具体的なポイントをいくつかの視点から解説します。
運用体制の構築
効果的な広告運用を実現するには、運用体制を整える必要があります。
適切なチーム編成と役割分担を行い、明確な目標設定をすることが成功への第一歩です。
チーム編成
インハウス化では、広告運用に特化したチームを編成することがポイントです。
チームには、データ分析やクリエイティブ制作、広告運用の各分野に精通したメンバーを配置しましょう。
それぞれの専門性を活かすことで、効率的かつ効果的な運用が可能になります。
具体的には、データ分析担当がターゲット層や市場動向を把握し、クリエイティブ担当は視覚的に訴求力の高いバナーや動画を制作します。
このように役割ごとに適切な人材を配置することで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。
役割分担とKPI設定
チーム内での役割分担を明確にし、それぞれの業務範囲を定めることが大切です。
同時に広告運用の成果を測るためのKPI(重要業績評価指標)も設定します。
KPIにはクリック率やコンバージョン率など、具体的で測定可能な指標を採用します。
そこで、「月間コンバージョン数10%増加」などの目標を設定し、それに基づいて各メンバーが責任を持って業務を遂行できるようにしましょう。
その結果、全員が同じ方向性で動きやすくなり、成果も見えやすくなります。
効果的な広告戦略
インハウス化後も成果を上げるためには、戦略的な広告運用も不可欠です。
特にキーワード選定とクリエイティブ制作は、広告効果に直結する重要な要素です。
キーワード選定のポイント
キーワード選定では、自社の商品やサービスに関連性が高く、競争率が低いものを狙うことが効果的です。
また、ターゲット層が検索しそうな具体的なフレーズやニッチなキーワードも積極的に取り入れてみましょう。
たとえば、「初心者向けオンライン英会話」など具体性のあるキーワードは、高いコンバージョン率につながりやすいです。
また、定期的に検索トレンドを確認し、新しいキーワードを追加する柔軟性も求められます。
クリエイティブの最適化
クリエイティブはユーザーの目に留まりやすく、行動を促す内容にしてください。
そのためには、視覚的要素だけでなく、キャッチコピーやボタン配置なども工夫しましょう。
また、ターゲット層ごとに異なるデザインやメッセージを展開することで効果が高まります。
たとえば、若年層向けにはポップでカジュアルなデザイン、大人向けには落ち着いたトーンのデザインが適しています。
こうした最適化によって広告効果が大きく向上します。
効果がでる広告運用
広告運用では継続的な改善が重要です。
一度設定した施策でも、市場環境やユーザー行動の変化に応じて見直し続ける必要があります。
細かな調整と迅速な対応力が成果につながります。
データ分析と改善
データ分析と改善はインハウス化を成功させるカギとなります。
正確なデータ収集とその活用によって、広告効果を最大化できます。
定期的な分析レポート作成
運用状況を把握するためには、定期的にレポートを作成して結果を振り返ることが重要です。
このレポートではクリック数やコンバージョン数だけでなく、それらの背景となる要因も分析します。
具体的には「特定曜日にクリック率が高い」などの傾向が見えたら、その時間帯に予算配分を強化する施策につながります。
このようにレポート作成は次回以降の改善施策立案にも役立ちます。
A/Bテストの運用
A/Bテストは複数パターンの広告クリエイティブやターゲティング設定を比較し、有効性の高いものを選ぶ手法です。
このプロセスによって最適解へ近づけます。
たとえば、「赤色ボタン」と「青色ボタン」のどちらがクリック率が高いか検証することで、小さな調整でも大きな成果につながることがあります。
テスト結果は次回以降にも応用可能です。
ディスプレイ広告をインハウス化するステップ

ディスプレイ広告のインハウス化を成功させるには、段階的な取り組みが重要です。
ここからは、具体的なステップを分かりやすく解説します。
広告運用の目的と目標の確認
インハウス化を始める前に、広告運用の目的と目標を明確にする必要があります。
これにより、取り組むべき方向性が定まり、成果を測定しやすくなります。
コスト削減
インハウス化の大きな目的の一つは、運用コストの削減です。
代理店に支払う手数料を省き、その分を広告予算や他のマーケティング施策に充てられます。
この結果、同じ予算でもより多くの広告配信が可能になります。
たとえば、年間100万円の手数料を削減できれば、その金額で新しいターゲット層への配信やクリエイティブ制作を強化できます。
ノウハウの蓄積
もう一つの重要な目標は、自社内でノウハウを蓄積することです。
代理店に依存せず、自社で運用知識やデータ分析力を高めることで、長期的な競争力が生まれます。
たとえば、ターゲティング設定やクリエイティブ最適化などの技術は、一度習得すれば他のマーケティング活動にも応用できます。
このようにノウハウ蓄積は、企業全体の成長につながります。
社内リソースの確保
インハウス化には人的・経済的リソースが必要です。
これらを事前に確保しておくことで、スムーズな移行が可能になります。
経済面
まずは十分な予算を確保することです。
インハウス化にはツール導入費や教育費、人材採用費など初期投資が必要です。
ただし、これらは長期的に見ればコスト削減効果で回収できるでしょう。
たとえば、新しいツール導入に50万円かかったとしても、それによって効率的な運用が実現すれば、短期間で投資回収が可能です。
人材
次に必要なのは適切な人材です。
広告運用にはデータ分析力やクリエイティブ制作力など、多岐にわたるスキルが求められます。
そのため、既存社員のスキルアップや新規採用を検討してください。
具体的には、データ分析が得意な社員やデザイン経験者がいるならば、その人材を中心にチームを編成することで効率的な運用が可能になります。
教育体制
さらに、人材育成のための教育体制も整える必要があります。
社内研修や外部セミナーへの参加などを通じて、社員が最新技術や知識を習得できる環境を整えましょう。
「Google Ads認定資格」など、広告運用に有益な資格取得を目指す研修プログラムなどは有効です。
このような教育体制によって、自社内で専門性を高められます。
必要なツール
効果的なインハウス運用には適切なツール選びも大切です。
それぞれの目的に合ったツールを導入することで、業務効率と成果向上が期待できます。
Google Analytics
Google Analyticsはウェブサイト訪問者の行動データを分析するためのツールです。
「特定ページへの流入数」や「コンバージョン率」を確認することで、どの広告が効果的か把握しやすくなります。
広告自動化ツール(Optmyzr, WordStream)
広告自動化ツールは運用効率を大幅に向上させます。
これらは入札調整やキャンペーン管理など煩雑な作業を自動化し、人手不足を補います。
たとえば、「Optmyzr」はクリック単価最適化機能で費用対効果を高められます。
競合分析ツール(SEMrush, Ahrefs)
競合分析ツールは市場動向や競合他社の広告戦略を把握するために役立ちます。
「SEMrush」などを使うと、競合他社のキーワード戦略やトラフィックデータを確認できます。
ディスプレイ広告の運用
インハウス化後も継続的な運用改善が必要です。
そのためにはデータ分析と施策改善を繰り返す仕組みづくりが重要です。
定期的なデータ分析と改善
定期的にデータ分析レポートを作成し、現状把握と課題抽出を行います。
その結果から施策改善案を立案し実行します。
このプロセスによって広告効果が持続的に向上します。
インハウス化 ステップ
ディスプレイ広告のインハウス化では、「目的と目標設定」「リソース確保」「適切なツール導入」「継続的改善」が重要です。
それぞれ計画的かつ段階的に進めることで、高い成果につながるでしょう。
インハウス支援ならデジマケスクール

ディスプレイ広告のインハウス運用を目指す方には「デジマケスクール」がおすすめです。
「デジマケスクール」では、現役のWebマーケターが設計した実践的なプログラムを通じて、広告運用の知識とスキルを効果的に身につけられます。
また、初心者でも短期間で実務レベルに到達できるよう工夫された教材と、15分以内のコンパクトな動画講義により、日々の隙間時間を有効活用した学習が可能です。
料金は月額2,980円で豊富な講座を受講できるため、費用対効果に優れています。
企業内での広告運用体制構築や個人のスキルアップに最適なので、ぜひ受講してみてください。
プロの伴走支援でディスプレイ広告の価値を可視化

ディスプレイ広告は、クリックだけでなく認知拡大にも貢献しますが、その「間接的な効果」を社内に証明するのは難しいものです。
「デジマケトレーナー」の伴走支援は、正しい効果測定方法の設定から、経営層にも伝わるレポーティングまでをサポートします。
月額2980円からという費用で、ディスプレイ広告の真の価値を可視化し、自信を持った予算投下を可能にします。
まとめ
ディスプレイ広告のインハウス化は、コスト削減や迅速な意思決定が可能になる一方で、運用負担や専門知識の必要性といった課題も存在します。
効果的な運用には目的や目標の明確化やリソース確保などが重要です。
また、継続的な改善とデータ分析を行うことで広告効果を最大化できます。
さらに、デジマケスクールのような学習プラットフォームを活用すれば、効率的にスキルを習得し、自社運用体制を強化できるでしょう。
本記事を参考にしつつ、ディスプレイ広告のインハウス化に取り組んでみてください。
デジタルトレンズへお気軽にご相談下さい。